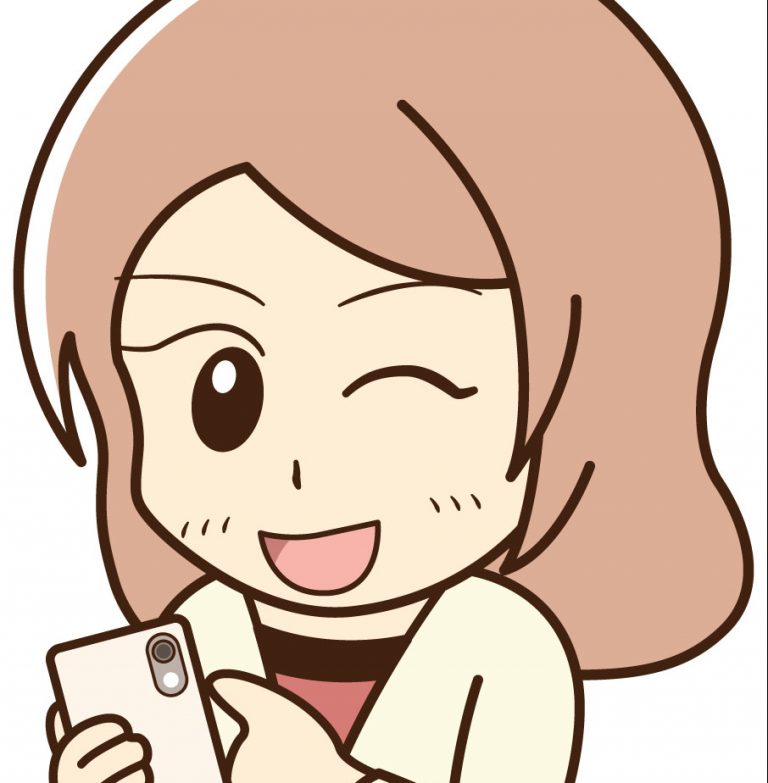ポプラ社小説新人賞一次選考通過作品ですので、「一次選考通過はこのぐらいのレベルかあ」と参考にして頂くもよし、奇特な方がいらっしゃれば気まぐれに読んで頂くのも良しかと思います。
管理人は長編しか書けないので、本作も400字詰め原稿用紙で400枚オーバーの長編となります。
このため、前後編に分けて投稿いたします。あらすじも下に載せますので参照いただければ。
このフォーマットでは読みにくいという方がいらっしゃれば、カクヨムと小説家になろうにも掲載していますので、以下のリンクをご参照ください。
それでは、拙作ですがよろしくお願いいたします。
あ、もし読んで下さった方がいらっしゃればここのコメント欄でもなろうやカクヨムからでも、何かしら感想があるととても嬉しいです!
カクヨム作品ページリンク
小説家になろう作品ページリンク
あらすじ
クラスメイトの唯が自殺した。唯に「いけにえ」と呼ばれつきまとわれていた高校生の恵太は、自殺の原因を探っていく。
死ぬ前の唯の不可解な行動、自分を幽霊だという女、人気ロックバンドのファンによる後追い自殺の噂…
真相を探る恵太の前に現れる謎の数々。
自称幽霊とともに、謎を追っていく恵太が目にした真実とは…。
【以下本編】
プロローグ
走るのを止めたのは、予感めいたものがあったからだろうか。弾む息を抑え、恵太は辺りを観察していた。古びた商店街の中でシャッターが上がっている店は多くない。目をこらすと、額を伝う汗が邪魔をしてくる。乱暴に拭った視界の先で、和菓子屋から出て行く黒髪の背中。考えるより早く足が動いた。
「幽霊!」
音もなく振り向いたのは、恵太が探していた幽霊に他ならなかった。一瞬目を見開いたように見えたが、すぐに感情の読めない眼差しが恵太に向けられる。
「勝手に逃げんなよ」
恵太は短く言葉を続けながら息を整えた。何も答えない幽霊を視界に入れたまま、考えを整理する。このまま終わらせてはいけないという確信があった。脳裏に唯の顔が浮かぶ。誰よりも強い芯があるのに、人を信じることに臆病だった。最後に見た泣き顔が、恵太の胸をまた締め付ける。
「なあ、幽霊」
振り払うように口を開く。死んだ唯に対して、自分ができることをようやく見つけた気がしていた。
第一章
一 坂井恵太が唯(ゆい)と出会ったのは高校一年生の秋だった。とはいえ唯のことはその一か月以上前から知っていたので、出会ったと表現する時期はもう少し前の方が適切なのかもしれない。恵太が秋だと認識しているのは、それ以前の唯の印象があまりに薄く、出会ったとするその日の印象があまりに濃いからだ。
その日までの唯は、三十人以上いるクラスメイトのうちの一人にすぎなかった。知っているのは、高校生になって数か月という、落ち着かないタイミングで転校してきた女子であるということぐらい。転校生ということで始めは気を遣って話しかける奴もいたが、特定の誰かと行動を共にする様子はなかった。日を追うごとに唯の机からは人が離れ、入学して最初からずっとそこにいたかのように一人で本を読む姿が定着していく。恵太も、異論なくその景色を受け入れた。
その、自然に人を遠ざけていった唯から、突然恵太は話しかけられたのだ。新聞部の手伝いをして遅くなった日だった。
グラウンドはすでに暗く、まばらに残ったサッカー部員がカラーコーンを片付けていく。普段は授業が終わったと同時に学校を出る恵太は、グラウンドの照明を新鮮に感じながら駐輪場へと向かっていた。
深く考えず、見知らぬ先輩の頼みで名前だけ貸したはずの部活。廃部にならないよう、書面上の人数合わせという話だったのに、定期的に駆り出されているのだから文句の一つも言いたくなる。入学式直後の浮足立つタイミングに付け込むという、先輩の策を恨んだ。
「坂井くん」
同年代ぐらいの、窺うような女の声。声の正体を思い絵描けない。小走りの足音が近寄ってくるのが分かり、恵太は振り向いた。
「遅いね、部活?」
顔を見て、自分に声をかけてきたのは人違いかと思った。この、丸い眼鏡と少し眠そうなトロンとした垂れ目。大きい目なのに、目力よりも人懐っこさを感じる。小川唯の上目遣いが、自分に向けられていた。
「よいしょ」と小さな声とともに唯は鞄を担ぎなおした。小走りになった拍子に、肩からずり落ちかけたらしい。学校指定の鞄は、恵太と同じ授業を受けているとは思えないほど本が詰め込まれているようだった。
「ああ部活、になるのかな、一応」
「一応? なにそれ」
「いろいろ事情があってさ。えっと、そっちは?」
呼び名に困って『そっち』で片づけた。言ってから『小川さん』が正解だったろうと気づく。
「私は図書室だよ。ちょっと借りすぎたかも」
と言って、重そうな鞄を抱え直した。本来は片手で下げられるはずが、よほど重たいのか両手で持ったり肩にかけてみたりせわしない。微かに鞄のベルトが軋む音がする。
「マジで? それ図書室の本かよ。そんな量全部読めんの?」
「教科書も入ってるけどね。ちょっと調べものしてるから、気になったやつ借りられるだけ借りちゃった」
思いがけず自然に言葉を交わしていた。というより疑問が多すぎて、それなりの会話を返している方が簡単だった。小川唯という転校生は、人との関わりを避けているのではなかったか。そう自分が認定しただけで、実際は違ったのか。
「調べものってどんな?」
疑問はあるが、それでも恵太は会話を成り行きに任せることにした。恵太が駐輪場の方を手で示すと、唯は頷いて歩き始めた。唯が向かう方向を確認したつもりだったが、その意図が通じたかは分からない。
「それは、坂井くんが頼みを聞いてくれたら教えようかな」
「頼み?」
恵太は足を止めそうになったが、唯の荷物を見てそのまま歩みを進めた。校舎の角を曲がって裏手に入れば駐輪場だ。重そうな鞄に体が振られている姿に気が気でなく、唯の自転車があるだろう場所まで急ぐことにした。
「そう、頼み事。坂井くんには、私と仲良くしてほしいの」
その言葉を耳にして、より平静に歩き続けようと心がける。止まっても足早になっても、動揺したのが伝わってしまう気がした。なぜ伝わらないようにしようと思ったのか、恵太自身にも分からない。
「なんだよそれ」
考えられる意図を探しつつ、苦笑いを浮かべた。例えば、下手くそな冗談とか。
「何って、そのままだよ。友達になって欲しいってこと。そんなに変?」
恵太は自然と腕組みになっていた。
いや、変っていうか。友達ってそうやってなるもんだっけ。考えが呟きになって口から漏れてくる。
「そもそも、なんで俺?」
なぜ、まともに話したこともない相手に突然そんな頼み事をするのか。転校してきた唯に気をかける奴はたくさんいたのに。
腕組みをしたまま俯く恵太の足元が、グラウンドからアスファルトに変わった。校舎の角まで、あと少し。
「それはねえ、正直に言っていいのかな」
大きな目が、いたずらっぽく瞬きをする。恵太に尋ねるというより自問自答しているようだったが、あっさり恵太に向き直った。
「これはね、イケニエみたいなものだから」
「イケニエって、生け贄?」
「そう。私なんかと友達になるの、みんな嫌がるから。でも一人も友達がいないなんて辛いじゃない? だから坂井くんにその役をやってもらおうと思って。クラス代表の生け贄ってとこ」
恵太は組んだ腕を解けなくなっていた。質問するとその度に謎が増えるので、何から解決すべきか分からなくなる。
「よく分かんないけど、友達になりたいやつはたくさんいただろ?」
「いないよ。私のことを知ったら、友達になんてなりたくなくなる」
暗い台詞と裏腹に、同じように話を続ける唯に調子を狂わされる。
「それでなんで俺なんだよ」
「それはね」
唯は肩に乗せていたカバンを両手に抱え直した。なぜか罰が悪そうに息をつく。
「坂井くん、頼まれたら断れない人でしょ。もしかしたら、私の頼みも聞いてくれるかもって思って」
唯がまじまじと恵太を見上げてきた。恵太は否定したかったが、新聞部の手伝いの帰りだという状況に言葉を濁らせた。頼まれたら断れないなど、自覚したこともなかったのに。怪しい占い師に素性を言い当てられた気分だ。
「それに」
続けようとする唯に、恵太は釘付けになった。内面を見抜かれているようで、今度は何が出てくるかと興味と不安が浮いてくる。
「生け贄なんて、何人も作るものじゃないでしょ? 私に話しかけてくる人、みんなグループだったから」
唯の意図を測りかねて、次の言葉を待った。
「だから、お願いするには坂井くんがいいかなと思って」
唯はごまかすように笑う。
「それって要は、俺がボッチってこと?」
恐らく唯が避けたであろう部分を、逃がさないとばかりに言葉にした。恵太は心の中で否定できる材料を探す。SNSアプリ内の登録五十人近くという数字が、根拠となってくれそうな気がした。
唯は、「いや、ボッチとまでは言わないよ」と曖昧に苦笑している。
「言わないけど、思っていると」
「そうじゃないって。ただ、坂井くんだったら『みんなで』とか面倒なこと言わずに相手してくれるかなと思ったんだよ」
少し語気を強め、唯は真剣に否定しているようだった。小川唯という生徒に、自分から話したり、何かを伝えようと必死になったりする一面があるとは。クラスメイトの誰も考えもしないだろうと、恵太は珍しいものを見たような目線を唯へ向ける。
なぜ、教室では人を遠ざけるのだろう。考えが追い付かないうちに、目指していた駐輪場に着いていた。誰よりも早く帰るのが日常の恵太には、目で数えられる程度の自転車の光景は珍しかった。
「小川さんの自転車、どれ?」
恵太は自分の自転車に荷物を乗せると、唯の方を振り返る。唯は鞄を両手に抱えたまま、棒立ちだった。
「私、自転車ないよ。バスだから」
そう言って早々と踵を返していく。早く言えよ、と舌打ちしたくなるのをこらえた。結果的に付き合わせてしまったことを嘆きたい恵太より早く、唯が口を開いた。
「今日はありがとね。よかったらまた相手してよ」
唯の呼びかけには答えず、恵太は尋ねた。
「小川さん、帰るのどこから?」
「正門だよ」
その答えにさらに肩を落とした。正門は真反対だ。女子に重い荷物を持たせたまま遠回りをさせてしまったのは、なんとも罰が悪い。恵太は腹をくくり、自転車を唯のところまで押して出た。
「俺もバス停まで行く。それ、乗せろよ」
唯は一瞬ためらった様子だったが、恵太が改めて促すと、「ありがとね、助かる」と大げさに天を仰いで喜んだ。唯から鞄を受け取って自転車のかごに入れようとしたが、縦にしても横にしても半分ぐらいまでしか入らない。かごが重みで外れてしまわないか、心配になるほどだった。唯はよほど身軽になったのか、大きな伸びと息をしてはにかんだ。恵太はため息をこらえ、かごから飛び出しかけている岩みたいな鞄を手で抑えつけた。
「よし、行くか」
恵太が自転車を前に押し出すと、唯も横に並んで歩き始める。沈黙が怖い二人歩き。恵太は、腑に落ちなかったことを聞いてみることにした。
「つか、ボッチがいいなら他にいるじゃん。男なら増岡とか」
「ボッチがいいなんて言ってないでしょ。根にもちすぎだよ」
呆れたように唯が肩をすくめる。
「それにさ、友達になってほしいんだよ? 誰でもいいってわけじゃないからね」
多少の段差で自転車はバランスを崩しそうになる。ハンドルを固く握って、恵太は耳を傾けた。
「坂井くんといるのが一番、面白そうって思ったから、かな」
「面白い?」
「そう。坂井くんは、頼み事を聞いてくれそうで、馴れ合いがめんどくさくなさそうで、且つ一緒にいて退屈しなさそうという、いくつもの条件をクリアした希少な人なんだよ」
唯がなぜだか得意げに、眼鏡に手を当て人差し指を立てる。理路整然とした語り口に、恵太は頭の片隅にあった可能性を捨てた。これが新手のナンパである可能性は無さそうだ、と。唯はあくまで理論的に、電卓を弾くように恵太を選んだようにみえる。転校した先で運命の出会いを経ての恋愛、など夢見がちな考えは微塵もなさそうだ。
「それって、俺になんか得はあんの?」
「え?」
唯の声が意外そうに上ずった。
「だって頼み事だろ? 俺が受けたとして、何かもらえるものとかあんのかって話」
頼まれれば何でも受けるというレッテルが気に入らなくて、意地悪く揺さぶりをかけた。
「あー、お礼の要求か。なるほど」
唯の口が真横に結ばれ、視線が答えを探すように宙を泳ぐ。
「ない」
「ないのかよ」
急に投げやりになったような唯の発言に、恵太は笑ってしまっていた。
「そうくるとは思わなかったな。うーん……お金なら払えるけど、それって友達? なんか怪しい関係?」
恵太に向けて言っているのか独り言なのか、曖昧に呟いている。真剣な表情なのが、恵太はまた可笑しかった。
「あのな」
「わかりやすいのは物なんだろうけど、友達になってもらう見返りの物ってなんだろうね。相場が分かんないな。検索したら出てきたり、しないか」
真剣になりすぎて、呼びかけも耳に届いていないらしい。早いところ問題を解決してやらないと、本当に電卓で金額を打ち出してきそうだ。恵太は今度こそ唯に聞こえるように声を張った。
「いいって、嘘だよ。そんなことに金遣うなよ」
唯の目が、窺うように恵太を見上げてきた。近くで瞬きをされると、睫毛が長く整った目だと気づく。
「ほんとに?」
「本当だって。ていうか本気にしないだろ、普通」
「そっか」
安心したように、唯は目を細めて俯いた。恵太はこれから、バス停まで何を話そうかと迷う。聞いてみたいことは山ほどあった。なぜ今日まで誰とも話そうとしなかったのか、誰も唯とは友達になりたがらないとはどういうことなのか。
本当は帰る方向が反対なのに付いて来たと知った時、恵太は唯の頼みを受け入れようと決めていた。理屈はどうあれ、同級生の女子に頼られて悪い気はしていない。
「それじゃ、よろしくね坂井くん」
小さな手のひらが差し出しされた。一つしか意図は想像できないが、恵太がためらっていると
「よろしくの握手」
と唯が念を押してきたので恵太はその手を取った。か細くて、儚い感触。すぐに唯の手は離れていく。自分でも気づかないうちに、その小さな手を目で追っていた。この後、何から話そうか。恵太は少しの間、考えようとしていたことを忘れていた。
二
待望の昼休みに、恵太は勝ち鬨を上げるように伸びをした。ようやく掴み取った開放感。その日は月に一回程度の周期でやってくる、恵太が持てる力のいくらかを授業に注ぐ日だった。より正確には二日ぐらい前から。
学期が始まってから中間テストまでのさらに中間点である今日、英語のミニテストが行われた。親のため息などの面倒ごとを防ぐよう、悪目立ちしない程度の成績を収めることが恵太の目指すところだった。そのために要所でだけは復習をし、普段の授業中は眠り続ける権利を勝ち得ている。ひとまず今回も、及第点といえる六割は取れているだろう。
「玉田のやつ、マジで宣言通りの問題出してきたな。最高だよ」
前の席の古橋が半身で振り返り、恵太の机に肘をかけてきた。同意を求められても、恵太は心当たりが無くオウム返しになる。
「宣言通り?」
状況を掴めていないことが明らかな言葉に、古橋はわざとらしく口をすぼめ、手を仰いでおどける。
「うわー、いたー。玉ちゃんトラップに引っ掛かる残念な奴」
「なんだよ、トラップって」
「あー、ガチじゃん。マジで知らないやつじゃん」
恵太の疑問には答えず、通りかかったクラスメイトに声をかけてまで言いふらし始めた。反応の声が響き、それを聞いてまた好奇の目をした連中が囃し立ててくる。さすがに苛立って、恵太は古橋の椅子を爪先で小突いた。
「なあ、教えろって」
古橋はもったいぶりながらも、恵太に同情のこもった目を向けながらネタばらしを始めた。
曰く、今日のミニテストで出たいくつかのところは、英語の担当教諭の玉田が授業の中で予告をしていたところだったらしい。その程度のことの何が、古橋たちを盛り上げているのかが分からない。
続きを聞いて、ようやく恵太はことの重大さを知ることになった。玉田は、声も体も小さく気が弱そうで、恵太たちと比較的歳が近いため「玉ちゃん」と勝手に生徒から呼ばれるような教師だ。その授業風景は無風。クラスの地味な女の子が嫌々教壇に立たされているような悲壮感があり、困らせるのは可哀そうという空気が流れていた。だから、スマホを見たり寝たりしている奴が大半とはいえ、授業が誰かに妨害されることもない。この構造は、玉田との暗黙の了解がとれていると誰もが思っていたが、実際は違ったそうだ。実は授業を聞いていない生徒を、玉田は決して良しと思っていなかったらしい。かといって面と向かって生徒に注意できない中でとった作戦が、例のトラップだ。
『予告したところは必ずそのままミニテストに高い配点で出す。その代わり、間違えたら追加のレポートを課す』という玉田の宣言を、誰かが「玉ちゃんトラップ」と名付けたらしい。祈るような気持ちでそのトラップとやらの対象問題を聞いたが、どう贔屓目に考えても何問かは間違えている。「ドンマイ」と肩を叩いて散り散りになっていく連中を背に、恵太は教室の一番後ろの席に向かった。
「お前、玉ちゃんトラップの話知ってた?」
顔の前に掲げるようにしていた本が下がり、恵太を見上げる唯の目が現れる。罰の悪そうな上目遣い。恵太は早々に答えを悟った。
唯の前の席の主はどこかへ行っているようだったので、机に寄りかかって唯を見下ろす。
「あ、その感じは、やっちゃった感じ?」
控え目に眉を上げる唯に、不満をぶつけようとしたところを後ろから抑えられた。両肩を乱雑に掴む感触が、振り返らなくとも相手を連想させる。
「よう恵太。レポート確定だって?」
親しみとからかいが込められた厚い手で、木田竜(たつ)海(み)が肩を鷲掴みにしてくる。唯にぶつけようとしていた不満そのままに、二人へ声を荒げた。
「お前ら、なんで教えてくれないんだよ」
恵太と唯が握手をしたあの日から、気付けば一緒にいることが多くなっていた三人だ。
恵太は実際のところ、唯と友達になると了承したもののどう接するべきか戸惑っていた。なにせ、唯は恵太以外の友達はいらないと真剣に言う。本当に恵太としか交流をもたなかったら、クラスの連中はどう思っていただろうか。
「いくら恵太が寝てるのが当たり前だからって、まさか知らないと思わなかったんだよ」
恵太の心配の解決にこの、ふんぞり返ったまま釈明している竜海の存在は一役買っていた。唯が恵太と二人だけで行動を共にするのと、竜海も含めた三人で過ごすのでは傍から見た印象が随分違っただろう。突然他人とつるむようになった唯に、不思議そうな視線を向けてくる奴もいたが、何日かすれば誰も疑問をもたなくなった。小川唯は人付き合いを多くするタイプではないが、坂井と木田のグループに属することにした、という評価が定着したらしい。
「ん、その様子じゃ唯も教えてなかったのか?」
言って竜海は恵太の肩を解放し、唯の方を窺った。
「まあ、ね」
苦笑して視線を逸らす唯の次の言葉に、恵太は注目した。ついでに竜海にも当たっているが、本心では唯を問いただしたかった。この二日間、恵太にテスト対策を教えると買って出たのは唯なのだから。
「教えてもよかったんだけど、それだと勉強にならないかと思って。あんな簡単なところ、まさか間違えないと思ったし」
暗に、そこまでできないと思わなかった、と言われているようで恵太は項垂れた。馬鹿にしているのではなく、唯は心底予想外といった面持ちで唇を尖らせている。
「完全にミスだ。教えてもらうやつを間違えた。やっぱ竜海にしときゃよかった」
自分の読みの甘さを呪う。思えば、唯は来る学校を間違えているのではと思うほどの成績優秀者だった。授業中、関係のない小説などを読みふけっているだけのくせに、当てられて答えに詰まったり間違える場面は見たことがない。恵太がそのことに触れると、前の学校ではとっくに終わっていた範囲だから、と涼しげに答えていた。小学校からの付き合いである竜海なら、恵太の平々凡々な学力を察してトラップのことも教えてくれていただろう。
「ごめんごめん、レポート手伝うからさ」
唯はあしらうように助け舟を出して笑った。レポートに関しては、竜海と一緒に悪戦苦闘するより唯の知識を頼った方が良さそうだ。恵太はあっさり前言撤回し、再び唯に手伝ってもらうこととなった。
「よし、レポートのこともなんとかなりそうみたいだし、飯食おうぜ」
竜海が待ちきれないとばかりに、自分の席へ弁当を取りに向かおうとする。恵太は呼び止め、唯と売店に行ってくるから待ってほしいと告げた。普段は弁当を持ってくることが多いが、母親のパートが早出の時はパンなどを買って食べるのがほとんどだ。唯はいつも決まって売店なので、最近は恵太も買って食べるときは一緒に行くのがお決まりになっていた。
「至急な」
急かすような言葉に反し、竜海はスマホに目を落としてすでに画面の中に意識を向けているようだった。
「竜海って、意外と体育会系じゃないよねえ」
売店に向かいながら、唯が肩をすくめる。中学生になったころから、竜海がゲームと漫画とアニメに情熱を注いでいることを知っている恵太からすれば、意外でもなんでもない。今だって、スマホのゲームでもやっているんだろう。お陰で多少の時間は気兼ねなく待たせられる。
「最初は絶対キャッチャーだって思ってたんだよ」
「キャッチャー?」
「そう。部活やってるのかとか知らないけど、きっと打てて守れるキャッチャーだって。それで、意外に足も早いの」
唯は歩きながら、架空の竜海の選手像を身振りをつけながら説明している。時々熱が入って恵太に遅れ、小走りになっては追いついた。
「唯って野球も詳しいのか?」
野球も、と言ったのは唯の幅広い知識を引き合いに出してのことだ。学業面も含め、唯は雑学豊富というかマニアックというか、漠然と生きているだけでは到底知りえないような情報をよく知っている、ということが最近になって分かった。
「私に知らないことなんてないからね」
小走りの流れのまま恵太の前に回り込んで、不敵に笑ってみせてくる。実際は、唯本人が言っていた話だと無数の本を読んでいるうちに身に付いた知識らしい。好奇心に駆られるまま目に留まったものを読み、気がつくと頭の中に入っているそうだ。恵太と一緒に帰ったあの日は、人体解剖図鑑や病理学など、小難しい本を大量に借りて帰っていた。医者や看護師になりたいわけでもないとのことで、つくづく変わった奴だと恵太は思う。
「ほんと変な奴だな、お前」
恵太が呆れたように言ってみせると、なぜか誇らしげに
「そう、変なんだろうね私」
と笑って返してきた。自覚はあるのかと思い、恵太は少し不思議な気分になった。唯の、行動と思考の差が腑に落ちない。
三人が話すようになった当初も、唯の言動には困惑させられた。教室で当たり前のように話しかけてくる唯に恵太が応じていると、周囲の視線をよそに竜海が会話に入ってきたのだ。唯に何も聞かず接したのは、歓迎の意を込めた竜海なりの気遣いだったのだろう。唯の方は、新しい仲間ができて喜ぶ、といった反応ではなかった。どこかよそよそしく、受け入れるべきかを迷うような態度。業を煮やした恵太がどういうつもりか問いかけると、唯は謝り、「私と仲良くなるのは生け贄だって言ったでしょ?」「やめた方がいいと思うけど、二人がいいなら友達が増えるのは嬉しいよ」と続けた。恵太と竜海が目を合わせて、意味が分かっていないのはお互い様であることを確認しあってから今日まで、三人の日々は何の波乱もなく続いている。
生け贄という物騒な言葉が意味するところは恵太と竜海には考え付かず、非現実的な響きすぎて気にも留めなかった。
自分と仲良くなりたがる奴はいないと、唯は言っていた。そんな妄想じみた、痛々しい決めつけをするほど浮世離れした人間かというと、そこまではズレていないと思う。だが事実、唯は頑なに恵太と竜海以外とは関わろうとしていない。目の前にいる、奔放に振る舞う姿と、やたらと閉鎖的な人付き合いの仕方が結びつかなかった。
考えた答えは出なくとも、食料は滞りなく調達でき教室に戻る。出たときと変わらない、場所と姿勢でいる竜海を見つけるのは簡単だった。唯もまっすぐ席へ向かっていく。
「竜海は、キャッチャー系男子に降格だね」
ん? と小さく声を上げると、竜海は何度かスマホを指で弾き、名残惜しそうに画面から目を離した。
「なんだって、何が降格だ?」
「竜海が思ったより全然動かないからキャッチャーは失格。でも性格と見た目はキャッチャーの素質があるからね。キャッチャー系っていう称号は与えられるかな」
竜海から恵太へ、助けを求める視線が送られてくる。恵太は、大丈夫、俺も分からない、と手で制した。
「残念だったな、キャッチャー系男子」
意味など分からないが、恵太は竜海に声をかけた。
「なんだよそれ、そんなことより早く飯食おうぜ」
「さすがキャッチャー系、動いてないけど一番腹減りキャラだね」
竜海の筋肉質なガタイは、今後もスポーツに使われることはないだろう。そんなことは本人の自由なのだが、言いがかりとも思える唯のネーミングが妙に納得できて、恵太は笑いを噛み殺した。
「うるせえよ。ゲームだって腹減るんだぞ」
言いながら竜海はにやけてしまい、唯も満足そうに笑っている。いずれ課されるだろうレポートの存在が引っ掛かりながらも、他はここ最近の日常的な光景だった。恵太と唯が握手をしたあの日から、少しずつ恵太の退屈は減っていっていた。
三
二年生になって一か月。恵太は肘をついて目だけは玉田に向けていた。一年生の時のレポート事件から、玉田のマンツーマンの指導を受けるに至ってすっかり存在を認識されてしまった気がする。授業中、頻回に目が合うので気楽に寝られなくなってしまっていた。
「ねえ、今日の玉ちゃんの髪かわいくない?」
「ちょっと聞いてみてよ。彼氏できた? って」
後ろの席で誰かが話しているのが、恵太の耳にも届いてくる。言われてみれば、確かに玉田の雰囲気はいつもと違っているように見えた。よほど興味を惹いたのか、控えめだった談笑は二人から三人、それ以上の声の輪へと広がる。
「あの、聞こえてますか?」
ついには玉田に見つかって、半分泣いているような顔で声が掛かった。
「センセー、今日かわいいね」
「え、あ、はい」
物怖じせず真顔で教師を褒める生徒と、受け入れてしまう玉田。チャンスを窺っていたかのように、一斉に教室のあちこちで弾んだ声が続く。
「はい、って言っちゃったよ」
「だってかわいいから、いいんだよ」
「誰か意識してるのかな?」
一年生の時のクラスは妙に大人びていたというか、生徒が玉田に合わせて授業の進行を乱そうとしなかった。二年生のこのクラスは、やたらと干渉的な奴が多いようだ。他人の作る暗黙の壁なんか気にしないで、クラスメイトにも教師にも踏み込むのが多数派になっている。同じ玉田の授業でも、授業風景は違ったものになっていた。
「坂井はアリ? 今日の玉ちゃん」
前の席から星井が振り返る。銀縁眼鏡越しの糸のような目が、好奇で満ちている。
「ナシ」
恵太が即答すると、「激辛評価じゃん」と笑い満足気に前へと向き直った。恵太からすれば、玉田である以上どう飾っても検討の余地があるとは思えなかった。
「なあ」
一向にクラスの喧噪が止む様子がないことに便乗して、星井が再度体を捻ってくる。恵太が視線を合わせると
「今チャンスだろ。動画見とけよ」
「バカ、見つかったらどうすんだよ」
恵太は苦笑いで首を振った。
星井は仕切りに、以前送りつけてきたアメフトの動画を見るように促してくる。恵太にはまるで興味のないスポーツだったが、星井はアメフトのルールや迫力、戦略性について語り始めると止まらない。あまり熱く語るので、一度ぐらいは試合を見てみるのもいいかもしれないと思うようになっていた。
次第に誰かが自重し、たっぷり時間をとってからクラスは落ち着きを取り戻していった。こまめに視線を向けてくる玉田を前に寝るのも難しく、恵太は教科書を立てた。内側に、唯から借りた本を重ねてある。今日の本は時代小説。先日借りたのは生物の本に音楽史に哲学書と、一貫性がない上にどれも難しく、読めた本はなかった。さすがに小説は読みやすいのではないかと期待したが、耳慣れない人物の名前が整理できずに諦めた。再度目線だけ玉田に向け、聞き取りにくくか細い声を理解することも諦めた。
昼休み、唯の席の前には恵太が座っているのが二年生からの当たり前になっていた。この、馴れ馴れしい人間の集まりのようなクラスですら、昼休みは誰も二人の間に入ってこようとしない。学年が変わって痛手と言えば、竜海が別のクラスになってしまった。恵太の頭を悩ませているのは、唯との付き合い方だ。竜海と三人でいたことで目立たなかった唯の生け贄制度が、クラスの中で違和感を隠せなくなっている。たびたび二人は付き合っているのかと尋ねられ、否定しても信じてもらえないか、冷やかされるかのどちらかといった具合だ。
「星井んち、めちゃでかいテレビがあるんだってさ。俺んちのショボいから楽しみだ」
状況は気に入らないがどうすることもできず、恵太は普段同様に唯に話しかけた。近く、星井の家にアメフトの試合や雑誌を見せてもらいに行く約束をしたことを話題に出す。
「テレビでテンション上がるって、昭和みたいだね」
コンビニあたりで買ってきたと思われるパンを頬張りながら、唯がからかうように言った。確かに、と恵太は唸って少し気恥しくなる。
「で、でも大画面で見るのがアメフトってのがいいんじゃん。迫力ヤバイらしいぞ」
「そうかもね。私もさすがにアメフトは詳しくないけど、見たらハマるかも」
「お、唯も星井の家に見に行くか?」
思いがけないチャンスだと恵太は思った。他人と関わろうとしない唯でも、その好奇心に火が付けばきっかけが掴めるかもしれない。
「え、私は行かないよ」
膨らんだ期待は一瞬で消え失せる。唯は悪びれた様子もなく、むしろ恵太の提案を不思議に思ったようだ。
「恵太知ってるじゃん。私は恵太か竜海としか話さないって」
「なあ、それもう、やめにしようぜ」
恵太は持っていた箸を弁当箱に置き、改まって唯を見た。吸い込まれそうなトロンとした目が、パチパチと瞬きをして止まる。
「どうしたの急に?」
箸と弁当箱が思いの他大きな音を立てたことで、恵太は自分の中に積み重なっている不満の大きさを知った。一年近い付き合いを通して、唯のことを面白く、頭がよく、そして分かり合える存在だと認めている。不満は他に何も無いのだ。ただ一つ、生け贄になるという奇妙な理由で交友を広げようとしない以外は。ただ一つの不満だからこそ、それが理不尽でならない。
「いつまでこうしてるつもりだよ。卒業するまでずっと続ける気か?」
唯は目を伏せ、詰まりながら答えた。
「それは、どうだろうね」
「なんだよそれ」
恵太は荒げそうになった声を、寸でのところで押し込める。代わりに椅子にふんぞり返ったが、「くそっ」と漏れた声は止められなかった。本当は怒りに任せて迫ってしまってもいいと思っていた。なんとか留めるに至ったのは、唯が、初めて見る暗い顔をしていたからだ。「いつまで?」と聞かれたときの一瞬、こみ上げる何かを小さな体に押し隠したように見えた。
重い沈黙が続き、二人の座っている横を通り過ぎようとした女子が、何事かと無遠慮な視線を向けてきている。
「なんだよ」
苛立ちを隠そうともせず女子を睨むと、そそくさと去っていく。教室の人はまばらで、適当な間隔で島のようになっているグループから二人の様子に気づいた者はいないようだった。恵太は睨んだ女子が誰かに言いふらすかもしれないと頭によぎったが、それ以上考えないことにした。
「恵太」
沈黙を破った唯は、いつの間にか目を閉じて考え込んでいたようだ。改めて目を見開いて、恵太を見据えてくる。何を言い出すのか、恵太は険しい顔のまま次の言葉を待つ。
「ダメなんだよ、私と仲良くなっちゃ」
それは前も聞いた、と言いかけたが、禁忌に触れることのような気がして止めた。唯に似つかわしくない歯切れの悪さが、ただ事ではないと訴えかけてくる。恵太は「ああ」とうつろな相槌だけを返した。
「でも、そうだね、ごめん。恵太と竜海が困ってるだろうなあっていうのは知ってたよ」
「別に、困ってるとかじゃなくてさ」
恵太は言いかけて、また口をつぐむ。困っているわけでないのなら、自分は何が不満なのだろう。頭のどこかで、唯にもきっと、何か理由があるのだろうと言い聞かせてきたはずなのに。
「じゃあさ、クイズしようか」
さも名案というように、唯が手を叩いた。唐突すぎて、恵太は顔をしかめるしかできなかった。
「クイズだよ。こんな重たい空気もう嫌でしょ? 私が問題を出すの。恵太は頑張って答えてね」
先ほどまでの気まずい時間を、唯はあっさり元通りにしようとしているようだ。恵太としても同意したいところだが、あまり簡単に切り替えられては面白くない気もする。さっきまでの思い詰めた様子は嘘だったのかと、文句を言ってしまいそうになる。
「クイズって言ってもただの遊びじゃないよ」
不服そうな恵太の思いを見透かしてか、唯が付け足した。
「恵太が正解できたら、生け贄がどういう意味なのかヒントをあげる」
「ヒント? 答えじゃなくて?」
思わず腰を浮かせたが、完全には納得できない提案だった。
「本当はヒントだって出したくないんだよ? でもまあ、私からできるギリギリのお詫びはそれかな。それ以上は無理。さあどうする? やる?」
なぜだか唯の方が乗り気になり、すっかり主導権を握っているようにみえた。
「ちょっと待てよ、俺が絶対知らないような問題を出されたら勝ち目ないじゃん」
「そこはちょうどいいぐらいの問題を出すよ。さ、弁当食べながらでもいいからさ」
促されるまま、恵太は蓋も開けていなかった弁当に手をつけた。つい数分前までは食べる気がしなかったが、今はなんとか喉を通っていく。
空腹が解決され始めることで、頭も冴えてくるのか妙案が湧いた。恵太がクイズに制限時間をつけないよう提案すると、唯はあっさり了承した。
「といっても恵太のクイズレベルが分かんないからなあ。まず、練習問題を出してみてもいい?」
咀嚼中の口の代わりに、親指を立てて答える。恵太は、どういう問題であろうと制限時間をつけないと取り決めができた時点で自分の勝ちを確信していた。たとえ今答えが分からなくとも、スマホで検索してしまえばいい。唯は当然文句を言うだろうが、目の前でスマホに触らない限り、調べたかどうかは証明できないというのが恵太の用意したシナリオだ。そもそも、ヒントぐらいもらって当然の立場と言えるのでこの程度の不正は許されるだろう、と都合よく片づけた。
「じゃあ練習問題。地球上にはたくさんの生物がいますが、笑うことができるのは人間だけです。さて、それはなぜでしょうか」
唯は、挑戦的に人差し指を立てて笑みを作った。
「なんだそれ、哲学的な話?」
「んー、強いて言うなら、社会学?」
「全然分かんね。社会学って地理とか法律とか?」
早々に考えることを放棄した恵太に、唯はため息をついた。
「いい? 大事なのは想像力だよ。なんでだろうって、想像するの」
「想像つってもな」
言われた通り、恵太は腕組みをして想像してみる。人間しか笑わない理由。確かに、犬も魚も鳥も虫も笑わない。
「あ、時々笑った顔の犬とか猫がテレビに出てるじゃん」
「あれは、そんな顔に見えるだけでしょ。嬉しくて笑ったりするものを対象とするよ」
うーん、とまた頭を捻らせる。何も出てこないので、口に卵焼きを運ぶ手が進むばかりだ。唯に負けた気がして癪だが、恵太は間違っているだろうと承知の上で解答を挙げておくことにした。
「人間が、頭がいいからとかそういうこと?」
「残念でした」
つまらなさそうに、唯は唇を尖らせた。
「全然わかんねえよ。正解は?」
「それは、私も知らないよ」
「はあ?」
当たり前のように、自分が出したクイズの答えが分からないと言ってのけた相手を恵太はまじまじと見た。不適切問題を出したはずの当人は、いつものことではあるがこの程度の抗議の目では動じない。
「恵太の答えが、私が納得できるものだったら正解にしてたよ。でも、恵太の答えセンスないもん」
「クイズの答えにセンスとか意味分かんねえよ。それに、唯なんかセンスどころか答えすら無いんだろ?」
「私? 私の仮説ならあるよ。本当に合ってるか知らないだけで」
「知りたい?」と小声で言って唯がにやけるので、聞いて欲しいんだなと恵太は感じた。「どうぞ」とだけ促した。
「私が思うに、人間って伝えたいから笑うんじゃないかな」
「伝えたいから?」
うん、と頷いた唯の口元が、薄く笑ったように見えた。時々唯が見せる、どこか寂し気で、微笑みだけ残して消えていってしまうのではと不安になる横顔。恵太はいつの間にか目を離せずにいたが、その感情を振り払うように椅子に座り直した。
「私はこんなに嬉しい、楽しいって伝えたくて笑うんだよ、きっと。こんな風に」
明りを灯すように、唯はぱっと笑って見せた。
「ね、楽しい」
なるほど、楽しそうだ。と、納得しかけたが負けじと恵太も反論する。
「でも、愛想笑いとかだってあるだろ。笑いたくなくても笑ったりとか」
「それは、本来の目的から外れちゃった悲しい技だよ。人間が嘘をつくようになって、そんな間違ったやり方もできるようになってしまったってこと」
「そんなの唯が勝手に言ってるだけだろ」
言いながらも、唯の手馴れているかのような切り返しに負けそうになる。実際、唯はこんな毒にも薬にもならないような議論を、自分の中で繰り返しているのではないだろうか。そう思うと敵う気がせず、恵太は付け焼刃の返答を止め、絶対の審判に助けを求めることにした。
「じゃあ、唯の答えが合ってるか検索してみるぞ」
「検索しても、答えは出ないよ。いろいろ説はあるけど、何が一番正しいかは確かめようがないことだし」
「なんだよ、そんなのクイズになってねえよ」
今にも画面に触るところだったスマホを、恵太は机の上に軽く放った。
「だって、調べてすぐ分かっちゃうようなクイズじゃ不正し放題じゃん。確かに答えがはっきりある訳じゃないけど、言ったでしょ? 想像力が大事って。恵太の考えた答えがなるほど、と思うものならちゃんと正解にするよ」
自分で手放したスマホを取り直し、恵太は恨めしく画面に目を落とした。妙案と思い編み出した必勝法など、軽く先回りをされていたということだ。唯にはどんな時も、恵太の一歩先、二歩先を歩いていると思わされることがある。
「まあ今のは練習問題だからさ。ここからが本番だよ」
納得していない、と顔をしかめる恵太に構うことなく、唯は次の問題を進めようとしている。
「と言っても、今の感じじゃかなりレベルを落とさないとアンフェアかな。恵太、結構クイズレベル低いって分かっちゃったからね」
「うるせえよ」
ようやく恵太は一言返して、手を止めていた弁当を再び食べ始めた。二問目を出そうとああでもない、こうでもないと、唯が頭の中で思案している声はだだ漏れになっている。
現れては泡のように消える呟きを背に、恵太は唯の問いについて考えた。気持ちを伝えたいから笑う? 正しいような気もするし、全く的外れなような気もする。そもそも、疑問に感じたことが無いテーマだ。
一体、唯はどこからこういう視点に行き着くのだろう。毎日大量の本を読みすぎると、世の中が人とは違って見えてくるのか。いつか、人の頭の中を図解できる技術が可能になったら、唯の頭の中を真っ先に見てみたいと思う。
「よし、決めたよ。これから出す問題が本番」
唯が恵太の肩を軽く叩き、注目を促した。キリ良く弁当も空になったことで、恵太は勝負に臨む態勢が整った気がした。
「よし、簡単なの来い」
力強く、手加減を要求。唯は「だいぶレベルを下げたよ」と苦笑いしながら出題へ入った。
「では問題。世界で最初の直線はどうやって作られたでしょう?」
「世界で最初の直線?」
聞きなれない組み合わせの言葉に、恵太は気の抜けた復唱をするしかできなかった。
「そう。人類がどうやって直線を作り出したかだよ。例えば地面に線を引くだけでもいいけど、どうやって昔の人は直線を引いたのか、それを考えて答えるという簡単な問題」
唯の言外に「ね、簡単でしょ?」と念押しの意図が伝わってくるので、恵太はつられて口を開いた。
「そりゃ、定規は無いからまっすぐに切った木を使ったりして」
言いながら、的外れな答えだと気づく。この答えでは、まっすぐに切った木はどうやって用意したかと言われてしまうだろう。唯が今にも口を挟みたそうだったので、恵太はその隙を与えないよう言葉を続けることにした。
「木をまっすぐに切るには、当然まっすぐな物が必要だから、他のまっすぐな物を当てたんだろ。例えば、腕、とか」
「それが答えでいい?」
余裕がありますとアピールしたげに、唯が声を浮つかせている。不正解であることは、唯の態度からも明らかなうえ、恵太も腕が正解では納得がいかないぐらいだ。どの部分をどの角度から見たって、人間の腕や足は緩やかに曲線が混ざっている。
「待てって、今のは仮説だろ」
ひとまず答えを取り下げて、他の案を考えた。まだ定規も無いような時代だから、恐らくかなり古代のこと。当時でまっすぐな物と言えば、土器などがありそうだが、その土器をまっすぐにした方法が分からない。そうなるとやはり自然にあったものだろう。貝殻、動物の死骸、石、考えたがどれもそうそう完全な直線と呼べるものがあるようには思えなかった。
「ヒントをあげるなら」
と、唯が前触れもなく言うので恵太の推理は途切れた。「腕とかって考えは悪くなかったかもね。人の体を使っても可能だよ」
自分からヒントを出して、なお余裕の表情を変えない唯に、恵太は一つの疑問が浮かんだ。
「なあ、ヒントまでくれるぐらいなら、俺の質問の答えを教えてくれよ」
「なんのことだっけ?」
目を見開いて、唯は分かりやすくとぼけて見せた。恵太は、苛立っていると思われないよう、唯に呆れている時のいつもの口調で言った。
「お前な、分かってんだろ? さっきまで俺が訊いてたことだよ」
恵太が横目で周囲を見渡すと、教室の中は食事を終えたクラスメイトがまばらに出入りしていた。一旦荷物を置きに来ただけの奴もいれば、机に伏したまま動かない奴、誰かの席の周りに集まって談笑を始めるグループなどほぼお決まりの流れだ。二人が話している内容は、よほど注意深く聞かないと周りには聞かれないだろう。それでも恵太は、再度あの質問を口にすることが憚られた。なぜ、唯は恵太と竜海としか話さないか。仲良くなってはいけないとはどういうことなのか。そんな非現実的な質問を誰かに聞かれたら、三人まとめて異端分子として扱われるような気がして息苦しかった。
「これはね、賭けなの」
突然、唯がため息とともに口を開いた。観念したとでも言いたげに、力なく作り笑いをしたように見えた。
「私にも、どうしたらいいか分からないんだよ。だから、神様に任せることにしたの。恵太が答えられたら、少しぐらい教えてもいいかなって」
「俺が答えられなかったら、賭けは唯の勝ちってことか?」
「それは、どうかな。誰が勝つとかって話より。そういうことをしてみたかったのかも」
唯の説明は要領を得ない。唯が隠しているものが何なのか想像もつかないが、唯が神様という言葉を使ったことの違和感が残っている。恵太が知っている唯は、理屈っぽさが時々面倒になるぐらい理詰めで物事を決める奴だ。神頼みという選択は、あまり似合わない気がした。抗えない何かが唯の背後にある気がして、恵太はそれ以上かけるべき言葉を見つけられなかった。
「分かったよ、クイズに答えりゃいいんだろ」
頷く唯が、ホッと気を緩めるのが分かる。恵太が再度、直線の疑問解決に頭を巡らせ始めた矢先。唯の肩越しに、無表情でこちらへ手を振る人影を見つけた。教室の入り口に結界でもあるかのように体は廊下に残し、顔と手だけが乗り出している。全く歓迎できない相手とタイミング。誰が見ても恵太へ向けられている視線を無視するわけにもいかず、渋々恵太は人影の方へ迎え出た。
四
教室の入り口に立ち、恵太は煙たく思っていることを隠そうともせず、竹内を見下ろした。
中学生ぐらいに見える背格好。顔立ちも幼いつくりのままだが、にきびと横に広がった鼻がアンバランスに目立っている。特に人望があるわけでも、画期的な企画を打ち出すわけでもないのに、盛り上げたい気持ちだけが先走って空回りしている小男。どうしてもと頼まれた時だけ部に顔を出す恵太ですら、竹内に対しての印象は出来上がっていた。この春から新しく新聞部の部長になったそうだが、消去法で選ばれたに違いない、と恵太は幽霊部員なりに推測している。
「やあ坂井くん、すまないね話し中のところ」
竹内がセリフじみた声と笑顔で言う。目を細めて表情を作っているつもりだろうが、恵太には引きつった顔にしか見えなかった。
「先輩、わざわざ直接来てもらって悪いんですけど、俺の答えは変わらないっすよ」
セールスマンを家に入れまいとするように、恵太は引き戸のレールでできた境界線から出ず答えた。竹内の用件は分かりきっている。先日スマホでメッセージが送られてきた件だ。廃部寸前の新聞部が、活動を校内でPRするために特別号を作るのだという。そのメインとなる記事の作成を、恵太にも手伝って欲しいという依頼だ。先代の部長から、坂井恵太は人数合わせだけの存在だと伝わっているはずなのに、とうとう教室まで訪ねてくるとは。いくら人手不足だろうとはいえ、恵太は理解に苦しんだ。
「そんなこと言わないでよ。これは、坂井くんにしか頼めないミッションなんだから」
「俺にしかできない?」
話しながら横目で唯の方を振り返る。唯は恵太たちの方を窺っているようで、目が合ったところで大げさにあくびをした。訳すると『退屈だ』ということだろう。恵太としても、さっきのクイズの答えを考えたくて竹内の存在が一層煩わしい。
「そう、坂井君にしかできない。なぜならこの事件の取材には、女性の力が必要でね。ところが新聞部には現在、女性がいないときた」
「それが俺になんか関係あります? 俺のこと、男って知らなかったんですか?」
皮肉を込めて分かりきったことを言った。いっそ怒って帰ってくれたら新聞部と縁を切れるいい機会になるのに。だが竹内は皮肉に気付かないのか、変わらぬ調子で話しを続けた。
「それはもちろん知ってるよ。そういうことじゃなく、坂井くんには誰か女性を紹介して欲しいのさ。我が新聞部は、悲しいかな女性というものに大変縁遠くてね」
「紹介?」
待たせたままの唯が気になりながらも、恵太は竹内の説明を聞くことにした。竹内が本気で恵太にしか頼めないと思っているのであれば、この機会に面と向かって断っておかないと後々面倒なことになりそうだと感じたからだ。唯は恵太がいないとき、一人で本を読んで過ごすことが多いのでこちらに構わずそうしてくれることを願う。
竹内の話によると、特別号は見た人の好奇心が刺激されるような、ミステリーや都市伝説の解明に挑む内容にしたいそうだ。革新的な内容になると竹内は息巻いていたが、恵太には間々ある話としか思えなかった。そしてメインの記事というのが、ここ最近ネット上で話題を目にするようになった、あるロックバンドのファンによる後追い自殺の件についてだった。恵太にはあまり興味のない話題だったが、バンド名と陰惨なワードが画面上に一緒に並んでいるところを、何度か目にしたことがある気がする。
事の発端は三年前、ヘイトロッカというロックバンドのメンバー一人が自殺をしたことに始まったという。世間的にはあまり名の知られていないバンドということもあって、テレビでの報道はほとんどなかったぐらいだ。波紋を呼んだのはその後、何人かの女性が後追い自殺をしたということが明るみになってからだ。
一時期は連日ワイドショーで取り上げられ、恵太もその一連の騒ぎは記憶にある。ところが連日話題を独占していたのがウソのように、ある日を境に報道されなくなった。竹内によればそれはさらなる後追い自殺を助長しないよう、報道規制がかかったためとのことだった。そして事件は次第に忘れられていき、後追い自殺をする者も最初の数人で終わったというのが世間で知られている話だ。だが、実際には自殺は止まっていない、と竹内は喜ばしいことかのように興奮気味に話す。奇妙なことにメンバーの自殺した七月六日になると、その一年後も二年後も、命日にファンが自殺しているというのだ。このままいくと二か月後の七月六日、今年も新たな自殺者が出るだろうと。これは竹内の独自調査というわけではなく、ネット上でまことしやかに流れている情報であり少し調べれば誰でも確認できる話らしかった。
「それでその話のどこから、女を紹介して欲しいって事になるんです?」
一向に話が核心の部分まで進みそうにないので、恵太は相槌を打つのをやめ、竹内に問いかけた。竹内は、「お、少しは興味が出てきたかな?」 と、どこまでも前向きな反応をよこしながら続ける。
「実はそのヘイトロッカは騒ぎの後に解散しちゃったわけだけど、ファンが作った独自の会員制サイトが生きてるんだ。しかも、女性限定の」
ここまで話を聞いて、ようやく竹内の言わんとすることが掴めてきた。そのサイトに入会して、内情を探れる者を探しているということか。
「サイトぐらい、女ってウソついて入っちゃえばいいじゃないですか」
「そう簡単にいかないから困っているのさ」
竹内はドラマかアニメの登場人物にでもなったかのように、芝居がかった抑揚とともに手を広げる。日常のやりとりでは違和感があって、鼻につくと恵太は思った。
「結構うるさいマニアが管理しているみたいでね。身分証明書の写真と顔写真を管理人に送らないと、入室パスワードがもらえない。そこで、我が部では一番女性の知り合いがいそうな君に白羽の矢が立ったというわけだね」
竹内が指をまっすぐ立てて恵太に向けてきた。払いのけたい気持ちを隠すため、恵太は視線を横へ逸らした。
「あの、その話長くなります?」
背後から、唯がひょっこり顔を出して話に入ってきた。てっきり本でも読んでいるかと思い、油断していた。この後の竹内の出方が予想できて、恵太は唯を追い返そうとしたが竹内の指の方が早く唯を指す。
「ほら、ここにぴったりな女性が一人」
人差し指を唯の前で止めたまま、したり顔の竹内が言った。突然の指名に、唯は怪訝そうに恵太の方を窺う。
「何事?」
「何事か、説明しよう」
意気揚々と、竹内が同じ説明を始めた。一度話したことでこなれたのか、恵太に話した時よりも淀みない。聞き流しながら、恵太はますます新聞部と竹内ともにまとめて辟易してきていた。先代の部長は、部の参加に否定的な恵太を引き込んだことに、後ろめたさがある様子が伝わってきた。自分の代で部が終わらないようにという願いも理解できたので、恵太は前部長の頼みを断ることができないでいた。しかし竹内の態度は厚かましいとしか感じられず、今すぐ退部届を出したい気持ちと前部長との義理との間で心が揺れる。隣からは、唯の生返事と愛想笑いが聞こえてくる。転校してきた当初は、クラスメイトに愛想笑いすらしていなかった記憶があるが、唯なりに改めているところもあるのだろうか。話に興味が無さそうなのは隠しきれていないが。
「ごめんなさい、私はやめておきます」
唯の迷いのない言葉で、どうやら竹内の話が終わったらしいことに気づいた。竹内は少し早口になって「お願いだ」「やっと見つけた頼めそうな人なんだ」「すぐ終わることだから」と繰り返した。
「うーん、女の人ならいいんですよね? 他の人にお願いしてもらった方がいいですって。先輩の友達とかの方が、話が早いですよきっと」
唯の提案は、現新聞部にとってハードルが高いであろうことを恵太は知っている。恵太にしても特別交友関係が広いわけではないが、女の協力者を挙げるという意味では資格がある部類に入るのだろう。幽霊部員である恵太のところまで竹内が頼み込みに来ているのは、他にその資格がある部員がいないからに違いない。竹内はそのことには触れず、代り映えの無い台詞ですがり付いている。
「そんなこと言われても」
不毛な問答が続き、唯が恵太に助けを求める視線を送ってくる。大体、竹内は事情を知らないとは言え依頼の相手が悪い。恵太と竜海以外、会話することすら否定的な唯が、胡散臭い新聞記事のための協力など応じるはずがなかった。恵太は頃合いと判断し、竹内に結論を伝えることにした。
「先輩、嫌がってる奴に何言ったって無駄ですよ。唯は特に頑固ですし。他に紹介できる女子はいないんで、諦めた方がいいっすよ」
二人の白けた空気がようやくいくらか伝わったのか、あるいは説得し疲れたのか、竹内は「はーあ」とほとんど話し言葉のようなため息を吐いた。
「もしかしたら誰かが死ぬのを止められるかもしれないのにさ」
今度は情に訴えかける気か。意外としぶといと若干の感心すら覚えたが、恵太に翻意させるほどのものではなかった。
「それ、どういう意味ですか?」
恵太とは違った反応を見せたのは唯だった。何が心に触れたのか、珍しく恵太と竜海以外の話の先を知りたがったのだ。その重大さに気づくはずもなく、竹内は続けた。
「我々は、そのサイトの登録者と会ってインタビューをしたいんだよ。もしその時に噂通り自殺願望があるような人が来たら、一応説得は試みるよね。本当に死なれたら後味悪いし」
「そういうことなら」
嫌な予感がして、恵太はしかめた顔で唯を見た。気づいてか気づかずか、唯は取り返しのつかないことを口走った。
「私、手伝います」
恵太には、唯の考えがまったく理解できなかった。
五
歩いていると、たくさんの直線が目に触れる。窓枠、電柱、排水溝、ブロック塀。顎先をさすりながら、恵太は考えを巡らせた挙句に首を振る。そのどれもが人工的であり、『人類最初の』というキーワードと結びつくとは思えなかった。何か手掛かりがあるかと製作工程を想像してみても、どれも定規なりコンピューターなり、既存の直線があって作られていることしか分からない。
唯から出されたクイズは、二日経ってもそれらしい答えを出せていない。今日は珍しく、唯が体調不良とやらで学校を休んでいた。恵太の記憶では初めてのことだ。星井や他の誰かにクイズの助けを求めようとも考えたが、切り出すタイミングがなく、結局放課後に至っている。
行き詰まりを感じ、授業後あえて駐輪場には直行せず、学校の周辺を歩いてみたところだった。唯が作った奇抜な問題に、自分の頭の固さを思い知らされているような気分だ。
恵太は思考をリセットするため、もう一問の問題を思い出した。唯の発想の傾向から、何か導き出せないかという苦しい作戦。
人間が笑うのは、楽しいと伝えたいからだ。
それが唯の出した問題と、仮説だ。反芻して、恵太は苦笑する。何の手掛かりにもならないという嘲りと、唯の独創性への驚きが入り混じっていた。
『ね、楽しい』
ぱっと笑った唯の顔が、容易に思い浮かぶ。確かに唯の楽しさが伝わった気がして、恵太は考えるほどその仮説が正しいように思えた。
学校の周りを一周したところで、我に返って目的を思い出す。直線の作り方を考えなければいけない。そう思って頭を切り替えようとしたが、楽しそうに笑う唯の顔がなかなか消えてくれなかった。
「変なやつ」
無意識に口に出して、恵太はまた苦笑いを浮かべる。
「よう、恵太じゃん」
聞き慣れた声に、反射的に振り返った。ほとんど同時に竜海が軽く肩を叩いてくる。竜海の後ろに、一年生の時のクラスメイトの姿が続いていた。
「何してんだ? 帰らないのか?」
学校の外で自転車に乗っていないことを不思議に思ったのだろう。竜海が眉を上げた。
「ちょっとな。あ、そうだお前。世界で最初の直線ってどうやったか分かるか?」
「ん、なんだそりゃ」
「唯が考えたクイズなんだけどさ、いろいろあって答えないといけねえんだよ」
「唯、か」
竜海が短くその名前を呼ぶ。一瞬浮かない顔になったように見えたのが、恵太は引っかかった。疑問を口にしようとした時、竜海の背後から声がかかった。
「お、坂井。ちょうどよかったじゃん」
上本だ。最後に話したのはいつか思い出そうとしたが、一年生の時ということ以外は見当がつかない。
「なんだよ、ちょうどいいって」
恵太の問いに、上本ではなく竜海が口を開いた。
「そうそう、恵太に用事があったんだ。今度俺ら、他校の奴らと遊びに行くことになってな。女側は四人なのに、男が三人しかいないんだよ。恵太来てくれよ」
「再来週の土曜日だぞ。いい話っしょ?」
上本が跳ねた長い毛先を揺らして、身を乗り出してくる。
「あー、どうするかな。考えとく」
「なんだよ、予定でもあんの?」
恵太が即答を避けると、上本が不満げに声を落とした。
「まあ予定っていうか」
恵太は無意識に断る口実を探していた。なぜそうしようと思ったのか理由も考えず、まずこの場を乗り切ることに力を費やした。続きの言葉を探すが出てこずに、あやふやなまま竜海と目が合う。竜海が加勢してくるかと、恵太は面倒な展開を予想した。
「ま、今決めなくてもいいけどな。他に行きたい奴がいたらそっち優先するぞ」
恵太の想像の中の、暑苦しいぐらいしつこく誘う竜海の姿はそこになかった。あっさり踵を返し、上本もそれに倣って恵太に背を向けた。上本が「じゃあな」と短い挨拶を入れ、恵太も手だけで応える。去り際に竜海が振り返ってきたが、何を言うでもなく上本の方へ向き直り去っていった。
恵太は駐輪場へと足を向け、再びクイズの答えへ気持ちを向ける。その間も、唯の笑った顔が離れてくれなかった。
六
季節の変わり目、霧雨が舞う外の天気も、室内に入ってしまえば実感が湧かない。冷房で作られた乾いた空気に、拒否反応のようなくしゃみが出る。平日昼間のフリータイムを利用してのカラオケボックス。学校行事の振り替え休日を、最大限活かした過ごし方だと恵太は自画自賛した。
曲を歌い終わって、軽く咳払いをした。もう知っている流行りの歌は一通り歌い尽くし、小学生のころに好きだったアニメの主題歌を思いつく限り挙げる。竜海の番が終わっては歌う。二人とも、引き延ばしが目的になっていることに薄々気づき始めている。薄暗いカラオケルームの中、会話もない代わりに歌手の新曲紹介のコメントだけが流れていた。
「次、入れろよ」
虚ろにモニターを眺めながら、恵太は意味のない強がりで曲が止まるのを拒んだ。
「待て、もう限界だ」
竜海が先に根を上げ、五人は座れそうな長いソファーに全身を預けている。L字型に二脚並んだソファーのもう一方で、恵太も思わず横になった。頬に座面のゴムの感触が当たって、普段は蒸発するはずの汗が肌に押し返されてくる。ことごとく嫌になって、恵太はすぐに起き上がった。ちょうど起き上がった目線の先にあったスマホが光ると、テーブルと反発し合ってしつこく音を立てた。考えるより先に手を伸ばし、画面に目をやる。
「唯かー?」
竜海が天井を仰いだまま、寝起きのような声を絞り出す。画面を睨んだままの恵太が「やっぱり」と呟くと、それだけで竜海には意図が伝わったようだ。
「来れないって?」
「ああ」
恵太は了解のスタンプだけ返すと、もう不快な音がしないようスマホをソファーに置くことにした。
「フラれたかー。せっかく珍しく恵太が誘ってんのにな」
「フラれたって言い方止めろよ。なんか、負けた気がするだろ」
「ん、フラれたんじゃないのか? それか夫婦喧嘩だったか?」
重たそうに体を起こしながら、竜海がからかいの笑みを浮かべてくる。
「お前までクラスの女みたいなこと言うなよ。そういうんじゃないって知ってるだろ」
この話題には辟易しているので、恵太は遠慮なく不快感を露わにした。
「恵太が違うって言っても、唯がどう思ってるかは分からないだろ? ちくしょう、俺だって彼女欲しい」
ソファーに横になって愚痴をこぼす竜海は、ふて寝をしているように見える。上本達と男四人、女四人で遊びに行くと言っていた件は、結局相手側の都合で中止になったそうだ。よほど悔しいのか、竜海はことあるごとに彼女が欲しいと繰り返すようになった。
竜海はリモコンを使って、モニターから流れてくる音を消した。代わりに、遠くから同年代と思われる団体のはしゃぐ声が聞こえてくる。聞こえてくる断片で、下ネタを多分に含んだ歌だと分かった。
「ほら、この謎の歌をBGMにすれば、頑なな恵太も恋愛を語る気になるだろう」
投げやりに言って、竜海は肩をすくめた。
「全然ならねえよ」
竜海は頷くと、天井を仰いで「おーい、曲変えてくれー。バラード頼むわあ」と届くはずもない掠れた声を送る。
「ダメだ、喉死んでる。ちょっと飲み物取ってくるわ」
立ち上がる際に、同じ飲み物でいいか確認してきたので恵太は同意して見送った。二人いても広すぎた部屋に取り残され、疲労した頭に竜海の言葉がぼんやり響く。唯がどう思ってるか分からない? 恋愛感情という意味で言っているのだろうが、恵太には唯にそんな感情があるようには思えなかった。そもそも、普段から唯が何を考えているのか想像し難い。唯に考えを見透かされることはあっても、常人が唯の思考回路に近づける日はない気がしている。
そう思うのは、最近の唯から受ける違和感の影響もあった。二、三週間前からだろうか。唯の様子がおかしい。竹内からの頼み事を引き受けると言った頃からだ。時々具合でも悪そうに俯いていたり、授業を休んだり。何か悩みでもあるのかと見かねて、恵太は三人でカラオケでも行こうと誘ってみた。唯は以前となんら変わらない様子の笑顔で「行く」と即答してからの今日だ。「少し遅れる」と連絡があったかと思えば、とうとう「やっぱり行けない」と断りの連絡が来たのが先ほど。
恵太としては内心、一度思いきり遊べばいつもの唯が戻ってくるのではと、根拠のない期待をしていた。現実は、ガス抜きをすることさえ叶わないという事態になってしまっている。
「お待たせ」
ドアが開き、竜海が両手にコップを持って戻ってきた。礼を言って受け取る。
「そんで、話す気になったか?」
二年生になって唯と接点が減った竜海は、唯の異変のことを話しても重く受け止めていないようだった。それよりも、竜海が見ていない間に二人に進展があったのではないかと勘繰っている。
「今日来ないのだって、二人で会おうって話じゃなかったのがショックだったんじゃないか? 最近調子がおかしいのも、二人の関係に悩んでるからだったら全部説明がつくだろ」
「あのな」
恵太がテーブルに頬杖をつき、竜海を見据える。何を思ったのか竜海は靴を脱ぎ、ソファーの上であぐらをかいた。
「なんだ?」
腕組みをして竜海が身を乗り出す。あぐらは、話を聞こうと姿勢を正した結果のものらしい。
「お前、彼女に毎日学問の話をされたいか?」
「は?」
竜海が間抜けな声を出し、意味が分からない、と首を捻って見せてくる。構わず恵太は続けた。
「唯はな、なんていうか、研究者なんだよ。好きな話題は生物学とか天文学とか、特殊相対性理論にはロマンがあるとかなんとか、そういう感じなんだよ」
「ああ、そういや一年のころもよくそんな話をしてたな」
「昨日話してたのはなんだっけ、ミトコンドリアについてだぞ。お前知ってるか? ミトコンドリア」
「知ってるぜ。なんか、SF映画かなんかで聞いたことあるからな」
一気にまくしたてるつもりだったが、恵太は一息ついた。竜海の返答が、昨日の自分と全く同じで親近感が先立ってしまったからだ。恵太が話題に付いていけないと、唯は馬鹿にすることもなく解説してくれる。そんなことが繰り返されると、自分は頭が悪いんじゃないかと不安になることがある。竜海の平凡な反応に、いくらか安心させられたところがあった。
「とにかくな、あいつと俺じゃ、見てる世界が違うんだよ。俺は唯をそういう相手として見れないし、唯も同じに決まってる」
黙って聞いていた竜海はいつの間にか空にしたコップをあおって、氷を一気に口を含んだ。ゴリゴリと音を立てて噛み慣らし、眉間にしわを寄せた。
「消極的だな。いいじゃん、毎日頭が良くなりそうな彼女ができるってことで」
無意識に出る舌打ちを止めることができない。竜海が「そんな怒るなよ」と軽い調子で返すので、恵太もそれ以上は追及しないことにした。
「でもな、その気が無いんならそんなに唯に構わなくてもいいんじゃないか? 今のお前、本当に唯が言ってた生け贄ってやつみたいだ」
「生け贄? どこが?」
「お前、とばっちり食らってるんだよ。気づいてるか? 唯のこと、俺のクラスのところまで噂が流れてきてるぞ」
まだ何を聞いた訳でもないのに、噂という言葉だけで不快な感覚が走る。
小学校の頃、仲が良かった友達の父親が元泥棒だと噂になったことを思い出す。噂が本当かどうかは分からないまま、恵太は何となく距離を置くようになった。ほどなくして転校していった彼は、噂が無ければ今も仲の良い友達だったのだろうか。
罪悪感に飲まれそうになって、恵太は思い出すのを止めた。
「なんだよ噂って」
恵太の食い入るような目線から、竜海は逃れるようにテーブルの上に転がっていたマイクを取り、手の中で遊ばせ始めた。
「唯が成績良いのは、誰か教師に贔屓されてるからだとさ。あいつ、今も授業を全然聞かずに本ばっか読んでるんだろ? しかも部活にも入ってないのに遅く帰るところを見られて、裏でこっそり教師に会いに行ってるんじゃないかって言われてる」
唯のことを少しでも知っていれば、なんの躊躇もなく否定できる話だった。唯はそもそも遥か上のランクの高校から転校してきているし、そうでなくても頭に事典が詰まっているような変人だ。授業など聞かなくとも問題ないだろうし、帰りが遅いのは図書室で調べものに夢中になった時だろう。それほど頻回にあることでもない。ひどく薄っぺらいこじつけ話に、恵太は乾いた笑いを漏らす。頭の中では、何も笑えることなどなかったが。
「誰が信じるんだよ、そんな作り話」
「唯のことを知らない奴だろうな。俺と恵太以外の二年生全員ってことだ。いや、もしかしたら他の学年でも知ってる奴はいるかもしれない」
くだらないと言って笑い飛ばすことを、竜海の強張った顔が許してくれそうにない。恵太は、鼻を鳴らして意に介さない態度を示すのが精いっぱいだった。
「それで、恵太の話だ。唯がお前と仲が良いのも、何か狙いがあるんじゃないかって噂になってる」
「狙いってなんだよ」
「知らん。何か狙いがあるってことにするだけで、噂を流したい奴からしたら都合がいいんだろうよ」
「誰だよ、噂を流したい奴って」
自分たちの知らないところで、根も葉もない話が伝播していっているのだろうか。圧し潰されそうなのに、どうすることもできない感覚。恵太は、怒りをぶつけるべき相手が見えないことの理不尽さを思い知った。
「これは俺の予想だがな。唯のことが気に食わない奴らがいるんだろうよ。一年の時のクラスメイトとかな」
竜海は始めこそ言い淀んでいるようだったものの、段々言葉を並べることを躊躇わなくなっていった。孤高を貫きながら成績優秀である唯への奇異の目、嘲笑、妬み。恵太や竜海との関係に対する好奇。知りたくもなかった誰かの黒い感情の話を、恵太は無言で聞いていた。
「まあ、唯の態度も良くないとは思うがな、俺は。だから恵太まで、付き合ってるわけでもないのに唯のワガママに巻き込まれる必要はないんじゃないかってことだ」
「唯ともう関わるなって言いたいのか?」
「そこまでは言わねえけど。ただ、ちょっと考えた方がいいんじゃないかと思ってな」
恵太は湧き上がる憤りを感じていた。無関係な連中の無責任な話にも、一歩引いたところから見ているように曖昧な忠告をする竜海にも腹が立つ。恵太ほどではなくとも、竜海も唯と一緒に時間を過ごした数少ない仲間のはずなのに。
「ほうっておけるわけないだろ」
なんとか声を絞り出した。他の部屋の客はいなくなったのか、いつの間にか歌声は聞こえなくなっている。繰り返し垂れ流される流行りの歌は、恵太の耳には入らなかった。
「これで俺まで関わらなくなったら、あいつのこと分かってやれる奴はいなくなるってことだろ」
いつか見た唯の思い詰めたような顔とともに、不安が頭をよぎる。何か、重大なことを見落としているのではないかという不安。もしかしたら知った顔をしている自分は、唯のことを何も知らないんじゃないか。彼女が抱える何かを、本当はもっと知りたい。それが、ぶつけようのない怒りとともに、こみあがってきた恵太の本心だった。
「それが生け贄みたいだって話なんだけどな」
竜海は恵太と目を合わさず、息を吐いた。気まずそうに宙を仰いでから、恵太にマイクを差し出す。
「悪かったな、面倒なこと言って。ほら、次の曲俺あんま知らねえから手伝ってくれよ」
「知らない曲入れんなよ」
ひったくるように恵太はマイクを受け取った。考える間もなく歌い出しになる。竜海のことも唯のことも、浮かんでくる顔をかき消すように声を張り上げた。
七
「三時すぎたね」
唯がスマホと睨み合いながら、せわしなく指を画面に当てる。何度か小気味良く画面を叩くと、スマホから垂れ下がった小指大の赤いピエロが揺れる。唯のスマホは、白いプラケースと赤い服のピエロの組み合わせがお決まりになっていた。
「来ないパターン、可能性高いかもな」
内心、相手が来なければいいと期待していた恵太は安堵した。入口の自動ドアが頻回に開いては、スーツ姿の男や、ご婦人達のお茶会といった顔ぶれが入ってくる。昼時を過ぎているとはいえ、駅前のファミレスは見渡せるうちの半分以上の席が埋まっていた。会計をしていくグループもあるが、定期的に新しい入店者が現れる。恵太はそのたびに入口を見つめ、同世代の女が現れないことを祈った。
「すっぽかし? 確かに、今のところ遅れるとも連絡ないけど……もうちょっと待ってみようよ」
そう言いながらも半ば観念したように、唯がスマホから顔を上げた。恵太とは対照的に、心から残念がっているようだ。
竹内からの依頼通り、唯はヘイトロッカのファンサイトに入会し、ファンの一人と今日の約束までこぎつけてしまっていた。何の義理も恩恵もない校内新聞の記事のためにここまで動く、唯の動機が恵太には理解できなかった。結局、恵太は唯について何も知ることができていない。カラオケに来なかった日のことや、暗い顔をしている時のことを聞いても、
『家の用事を頼まれちゃって』
『考え事ぐらいすることあるよ』
と言ってカラっと笑う。恵太にはそれが真実のようには思えなかった。唯の指に絡まったピエロが、嘲笑っているように見える。
来客を知らせるチャイムが鳴り、恵太はもはや無意識に入口へ視線を向かわせる。物思いが消え去ったのは、目に留まった姿が探し人の条件そのままだったからだ。茶髪が肩にかかった黒光りするレザージャケットを羽織り、下に黄色いシャツ。自分のスタイルを見せつけるような出で立ちの、恐らく女子高生。だが、主張の強い服装とは違い、表情はあたりを見回して落ち着かない。恵太と唯は声をかけるべきか迷い、視線を交わせ合った。待ち合わせの相手である確証が無い。唯がなぜか小声になって「連絡してみる」とスマホに目を落としたところを恵太は制した。レザージャケットのポケットから、スマホを取り出したのが見えたからだ。恵太が人違いであることを願う間もなく、唯のスマホの着信音が響いた。
赤いリップが映える口からストローを離すと、氷が崩れて音を立てた。柳(やなぎ)莉(り)花(か)と名乗った彼女は、席についてからの短い間に最初の一杯を飲み干してしまったようだ。白い指の先、恨めしそうにストローを弾いた爪も赤。細身のスタイルと輪郭から受ける華奢な印象を、チークの明るさが和らげている。恵太は初めの二、三言以外は口を開かず、二人の会話の聞き役に徹していた。
「ウチの学校に新聞部なんかあったんだ」
それが彼女の最初に漏らした感想だった。新聞部と名乗った恵太を前にして、悪びれる様子もない。
「ごめんね。どうしても、会って話を聞きたくて」
「ホント、フツーに言ってくれたらこんな気合い入れなかったんだけど」
首を斜めにし、莉花が自分の服を指して言う。唯は申し訳なさそうに言葉を変え、同じような詫びを繰り返した。その内容から、唯は新聞部の取材ではなくファンを装って会おうともちかけたらしい、と恵太は察した。
「ま、いいよどうせ暇だし。それに、ヘイロのことをカッコよく紹介してくれるんならアリかも」
「うん、頑張ってみる」
恵太は黙ったまま、唯に抗議の視線を送る。俺は手伝わないぞ、と固く誓った。
「えっと、まずヘイトロッカってどんなバンドなのかな?」
その質問を皮切りに、徐々に鼻息を荒くする莉花の独演会が始まった。ヘイトロッカ、通称はヘイロだそうだ。莉花が中学二年生の頃に聞き始めたことから始まり、ほとんど全ての曲を作っていたアキトというメンバーが死んだことまで触れていく。特にアキトの話に入ると、唯の相槌が追い付かないほどの勢いだった。
「私が一番好きなアキトはね、ライブで歌う前の時。ファンの皆に話しかけてくれるんだけど、それがヤバいの。なんていうかね……」
「ロマンチックな感じ?」
唯の補足に莉花は頭を捻らせる。楽し気に指でトントンリズムを刻みながら、言葉を探していた。
「そうじゃなくて、あー、なんて言うんだろ」
「エロい感じ?」
唯の突飛な答えに、恵太は咳き込みそうになる。恵太の動揺をかき消すように、莉花が手を叩いた。
「そう! すごいね、分かってるじゃん!」
マジかよ、と恵太は口先だけ動かした。
「ロックは通常、男性のセクシュアリティと攻撃性を含んでいる」
唐突に呟く唯に、恵太と莉花の注目が集まる。
「あ、えっと、ロックとは何かって一応調べて来たの。そしたら昔誰かが、そんなことを言ったんだって。だからエロいのかなって思ったの」
「へー、やるじゃんそいつ。昔の人の割には、できる人だったんだね」
能天気に笑う莉花を横目に、恵太は半ば呆れていた。唯の一貫した研究心に気が滅入る。ロックが何かを調べるため、図書館を奔走する姿が目に浮かんだ。
「てか、そんなこと調べてきたの?」
遅れて、莉花が瞬きを繰り返す。頷く唯を見て、改めて驚きの声を大きくした。
「そんなの、考えながら音楽聞くやついないって」
「でも、ロックってどんなのか全然知らなかったから。勉強した方がいいかなって思って」
莉花は珍しいもののようにひとしきり唯の顔を眺めると、耐えきれないといわんばかりに声に出して笑った。
「ロックが何かとか? 別にそんなのどうでもいいんじゃない? なんていうか、スカっとしてカッコいいから聞くんじゃん。好きなことなんて、気軽で自由だからいいんだって」
「自由、か」
唯は噛みしめるように呟いた後、「それもそうかも」と言って口の端を上げた。
「絶対そうだよ」
莉花の言葉に後押しされたのか、唯は小さく笑った。
始めのぎこちなさが薄れ、テンポのよい会話が続く。恵太は次第に気を緩めていき、耳だけ向けて会話を追っていた。弛緩していた流れが急に変わったのは、唯が本題の後追い自殺の件に触れた時だ。
「後追い自殺なんかまだあると思ってんの? あんなの頭おかしい奴が勝手にやってるだけでしょ。ほんと止めてしいんだけど」
莉花は途端に顔をしかめ、一息で言い切った。
自殺者が三年続いたことに関しては、ファンの間で知らない者はない常識だそうだ。ただ、なぜ三年経っても自殺者が出るのか、その理由は分からないと莉花は話した。
「私だって、アキトが死んだ時はもう生きてる意味ないって思ったけどさ。しょうがないじゃん、そんな簡単に死ねないし」
肩にかかった茶髪を指で遊ばせて莉花は言った。
「もう、今は死にたいって思わない?」
唯が躊躇なく踏み込むので、恵太は慌てて気を張ることになる。その心配をよそに、莉花はそれまでと変わらない様子で続けた。
「まー、生きててつまんないし、とは思うけどね。でも死ぬのもめんどくさいじゃん。しかも、それならアキトが死んだ時に死ねって話だよね。タイミング逃したって感じかな。ウケる」
生き死にの話とは思えない軽さで莉花は手を叩き、一人で笑った。恵太は不慣れな愛想笑いをしておいた。
莉花の隣に目を移したところで、恵太は思わず前かがみになった。唯の顔が、見過ごせないほど青ざめて見えたのだ。手を口に当て俯く姿が、絶叫を無理やり押し込めているようにすら感じる。
「唯、どうした。大丈夫か?」
たまらず恵太は声をかけた。唯はハッと正気に戻ったような顔で、「ちょっと眩暈、かな? もう大丈夫だから」と取り繕った。
「大丈夫じゃなさそうだよ。顔色おかしいもん」
莉花は俯く唯に顔を近づけて覗き込むと、背中をさすり始めた。それまで気ままに話していたのが嘘のように、莉花は真顔で唯の体調を案じた。
「スマホ、触る元気ある? 私のⅠDあげるから続きは調子がいい時にしなよ」
「いいのか?」
予想外の提案に、恵太は正直に疑問を口にした。初対面でしかも騙された相手だというのに、莉花は心配そうに唯を見つめたままだ。
「まあね。私、意外と悪い奴じゃないし」
自分で言ってのけるとは思わず、恵太は同じ感想をもちながらも曖昧に返した。その反応が不本意だったのか、莉花は「私もヘイロの話するの、楽しかったんだよ」と付け加え笑った。
「ごめんなさい、せっかく来てもらったのに」
青ざめたままの唯の、消え入りそうな声。唯なら無理にでも続けると言い兼ねないと思ったが。その心配をする余地もないほど生気の尽きた声だった。
恵太と莉花は代わる代わる病院へ行くように声をかけたが、唯が頑なに「眩暈がしただけ」「もう大丈夫」と繰り返すので、最後は根負けした格好になった。確かに、そうこう言い合ううちに唯の顔色は血色を取り戻してきたようにみえる。
結局、インタビューは日を改める、病院へは行かないということで三人は合意した。
「最後にもう一つだけ、聞いてもいいかな」
連絡先も交換し合い、後は席を立つだけというところで唯が二人を呼び止める。諦めが悪いぐらいの方が唯らしい気がして、恵太は妙に安心した。莉花も拒否することなく、帰り支度のためにバッグへ伸ばしかけた手を止め唯を見据えた。
「後追い自殺は、まだ続くと思う?」
「さあ?」
間髪入れずに莉花が声を漏らす。後追い自殺の話はよほど煩わしいのかもしれない。一度はやり過ごそうとした様子だったが、肩をすくめて付け加えた。
「知らないけど、普通に考えたらもう死なないんじゃない? 今更死ぬの、意味分かんないじゃん」
もっともな意見だと恵太は感じた。竹内はもっとオカルトの臭いやセンセーショナルな話を期待したのかもしれないが、莉花の言っていることはヘイトロッカのファンでなくとも抱く感想の範囲内だ。記事にするには収穫などほとんどないような結果になったが、恵太にはどうでもよかった。あわよくば、唯が頑なに作る他人への壁を、莉花が打ち壊してくれるのではという期待の方が勝っている。
「そうだよね」
唯が繕って笑ってみせる。恵太は、確かにある胸騒ぎのような感覚に顔をしかめた。唯に抱く、また何かを押し隠されたのではないかという疑念。全て、気のせいでありますように。唯が繰り返す、体調が悪いだけだという名目に縋りたかった。
八
竹内にインタビューの内容を話すと、恵太の予想とは違い「これでいい記事が書ける」と息巻いた。曰く「リアルな真実が書ければいい」とのことで、めげる様子のない姿に恵太の方が肩透かしを食らった気分だった。
莉花とのインタビューは続きがあるはずだが、唯はそのことに触れようとしない。恵太からすれば、唯と莉花が関わる機会が途絶えているのは惜しい気がしたが、竹内から催促を受ける必要が無くなった喜びも大きかった。
もう一つ、恵太には穏やかに日常を過ごせるようになった理由がある。唯の『眩暈』や『体調不良』を聞かなくなり、竜海とも三人で会う機会がもてたのだ。近所のショッピングモールで買い食いをする唯は、恵太たちがよく知っている知的で奔放な唯だった。
変わったままのことと言えば、二、三日に一度、唯が授業に出てこないことだ。出てこないといっても、丸一日いないのではなく、一限だけ抜けたり、時には午前全くいなかったりと規則性は無いようだった。
唯は「さぼり癖がついちゃって」と言い、「成績優秀者の特権だから、恵太はマネしないでね」とおどけてみせた。竜海から聞いたあの噂が、唯自身の耳にも入ってしまって落ち込んでいるのではないかと勘繰りもしたが、取り越し苦労だと思えるようになるまで時間はかからなかった。
六月に入ったとはいえ、日によってまだ肌寒い。教室内の服装は統一感が無かった。この日も思いの他寒く、母親の忠告を無視して学校指定のカーディガンを置いてきたことを後悔する。
机に突っ伏して国語の授業をやり過ごそうとしていた恵太だったが、背中を抜ける寒さにたまらずくしゃみが出た。頭を持ち上げた先の、黒板の上の時計は大して時間が進んでいない。変わり映えのない授業を背景に、寝直そうと迷わず腕へ顔を沈めた時だ。ふと、斜め前の席の宮下の椅子に掛けられたカーディガンが目についた。せっかくある上着を着ないでおくとは、宮下の気が知れない。例年以上に二転三転する気候の中、寒さを侮らなかった黒服陣営と、侮ってしまった白服陣営の構図のはずなのに。恵太は、着ないなら貸せと心の中で呟く。現実は、大それた頼みができるほど宮下と親しくもない。
まどろむ頭で意味もなくカーディガンを視界に入れていると、背中のあたりに黒い髪の毛が付いていることに気づいた。探せば探しただけ、髪の毛を見つけることができた。首元の位置から始まり、見えるところに未探索の場所が無くなったところで、我に返る。三分ぐらいは時間を潰せただろうかと思いつつ、恵太は申し訳程度に机に広げてあったノートに目を移した。白地を横切る、黒い線。指先で弄ぶと、弧を描いたり、張り詰めた線になったり。
惰性で何度か同じ動作を繰り返し、恵太は何か引っかかるものを感じていた。すぐに、その正体に気づく。頭の隅に追いやられていた難題。唯のクイズの答えだ。世界で最初の直線の作り方は、これではないのか。髪の毛を引っ張ってできた線を、粘土か何かに刻み付ければ、まっすぐな型が作れそうだ。髪の毛でなくとも、細長い糸のようなものでもいい。いずれにしても、どちらかを使ったとしたら。恵太は正解を確信した。
この答えなら、ようやく唯の理不尽なこだわりのヒントがもらえるだろう。それだけではない。日ごろ唯が話している内容をほとんど理解できていない恵太は、数少ない見返せる機会だとも思った。
ふと視線を感じて横の女子を見ると、慌てたように目を逸らされた。恵太は初めて、自分がにやけてしまっていたことに気づき咳払いをする。髪の毛を手先で弄びながら、残りの授業時間が過ぎるのを待った。
授業が終わり、放課後になったところで恵太は唯に声をかけた。他にも何度か声をかけるチャンスはあったが、ヒントとやらをじっくり聞けるようこの話題はとっておいてあったのだ。途中で唯が早退でもしないかだけが心配だったが、今日は『サボり癖』とやらは発揮しなかったようだ。クイズの答えを唯に投げかけると、
「きっとそうだと思う。私と同じ答えだね」
とあっけない返事が返ってきた。
実際には諸説あるそうだが、何であれ共感できるものなら正解にするつもりだった、と以前にも聞いたような説明が付け加えられる。一人でうんうん頷いていたかと思うと、唯は笑みを浮かべて
「やっと辿り着いたね。正解おめでとう」
と手を叩いた。指先だけで、二拍ぐらいの簡単な拍手。自分の席から立ち上がったところだった唯は、そのまま机にスカートだけもたれた。
「正解ってことは、ヒントってやつがもらえるんだな?」
期待していたほど大きな反応は無かったが、恵太は負けじと本題の方へ切り替える。
「もちろん。嘘はつかないよ。ちょっと待ってて」
唯は鞄から手のひらに収まる大きさのメモパッドを取り出した。飾り気のない、事務用のそれに何かを書き連ね、破り取る。
「はい、これ」
差し出された紙を、戸惑いながらも受け取る。女子高生らしさとは無縁の、可愛げのない走り書きだが文字は認識できる。一目でその数字の羅列が示すものは分かったが、唯の意図は想像し難かった。
「電話番号? 誰の?」
ハイフンを挟み、見慣れた距離感で区切られた数列。携帯電話の番号であることは間違いないようだった。
「幽霊だよ」
唯は微笑んだままだが、決してふざけているようではなく、恵太をまっすぐ見て言った。
「いや、意味分かんねえ」
「意味は分からなくてもいいんだよ。大事なのは、それがヒントになるってことでしょ?」
恵太は何か仕掛けがあるのではとメモ用紙を裏返したり逆さまにしたりしてみたが、電話番号という以外の意味は見出せなかった。
「誰だよこれ。どうせかけたら怪しいとこに繋がるんだろ」
「だから、幽霊に繋がるんだって。ただ、そう簡単には出ないと思うけどね」
聞きたいことが多すぎて、疑問符ばかりが頭の中を行き交う。結局、浮かんだことから挙げていくしかなかった。
「だから幽霊が誰だっての。唯の知り合いか?」
恵太の問いに、唯は含み笑いをこらえるように上ずった声で答えた。
「幽霊は幽霊だよ? ネットで見つけた番号なんだけどさ。死んだ人なら答えを知ってるかもしれないでしょ。何せ、私たちの常識なんか通用しない相手だろうし」
「お前、本気で言ってんの?」
恵太が知っている唯は、自分で持ちかけた提案をからかいでお茶を濁すほど不誠実な人間でははない。本気で言っていると分かっているからこそ、恵太は困惑した。
「あんまり難しい顔しないでよ」
となだめられても、ヒントがさらに意味不明では険しい顔つきになるのも無理はなかった。
「ごめんね恵太」
さすがに恵太の不満を察したようで、唯が弱々しく呟く。
「でも、本当だよ。その番号に電話すれば、きっと恵太の知りたい答えが見えてくるから」
真顔で訴える唯に、恵太はそれ以上追及できなかった。得体の知れない電話番号は不気味だったが、一度通話を試みてから文句を言っても遅くはないか、と自分を納得させることにした。
「分かったよ、電話すりゃいいんだろ」
「待って」
ポケットからスマホを取り出したところを、唯の声が止めた。
「絶対に、誰もいないところでかけて。人がいるところでかけるとね、大変なことになるんだって」
「大変なこと?」
「そう。ネットに書いてあったの。まあ幽霊に繋がる電話だからさ、呪いとか祟りとか、そういうことじゃない?」
恵太は今度こそ唯が冗談を言っているのではと疑いたくなった。唯は変わらない口ぶりで、こんな非現実的な話を信じるよう語りかけてくる。ヘイトロッカの後追い自殺よりも、よほどオカルト色の濃い話になってしまった気がした。
恵太は今一つ大事なものと思えないメモをヒラヒラはためかせ、ため息をついた。
真剣な目のままの唯を見る。確かに、読んでいる本の話を聞くと雑多で、懐が広いと言えばそうなのかもしれないが。ネットで拾った電話番号と幽霊話を信じろというのは、唐突で根拠が無く唯らしくないとも思える。延々と巡る考え事に収集がつかないまま、ひとまず恵太は番号をスマホに登録した。唯が改めて
「誰もいないところでかけてね」
と念を押してくる。恵太は曖昧に相づちを打った。
九
家に着くと、恵太は靴を脱いだなり目の前の階段へ向かった。階段の左脇に伸びる廊下の先には、台所で慌ただしく過ごす母親がいるだろう。確認もせず二階の自分の部屋に上がるのはいつものことだが、今はなおのこと歩みを止めたくなかった。制服を脱いで部屋着に袖を通す間も、唯からもらったメモのことが気になっている。
部屋の中にはベッドに机に本棚にテレビとゲーム機。必要な物以外はクローゼットの中にしまってある。異質なものといえば中学時代にしつこく誘われて買ったギターぐらいだ。誘ってきた当人が早々に飽きてしまい、インスタント式の軽音部は数日で自然消滅した。自分が弾いている姿を想像するたび、軽音部を存続させるよう手を尽くせばよかったのかもしれないと思い、釈然としない感覚が湧いてくる。未だに見えるところに置いてあるあたりが、未練の表れなのかもしれない。
恵太はベッドになだれ込み、仰向けでスマホをかざした。一、二回操作すれば、つい数十分前に唯からもらったばかりの番号が表れる。意図することなく、唯の言った通り誰もいないところでかけることとなっていた。恵太からすれば普段通り放課後を過ごしているだけだが、この状況なら唯も幽霊とやらも文句はないだろう。あとは目の前にある画面の、受話器のマークに触れるだけで電話がかかる。
恵太は念のため非通知の設定にして、受話器のマークに触れた。ごく平凡な、耳慣れたコール音。見知らぬ相手に繋がった場合は平謝りするしかないだろうと考えたが、その心配を嘲笑うようにコール音が続く。だんだん耳元から気持ちが離れていく中、突然音が止み、恵太は身構えた。だが、すぐに拍子抜けに変わった。第一声を聞いただけで分かる、ありふれた留守電のアナウンスだ。恵太は反射的に通話終了の操作をし、仰向けに転がって脱力した。
「誰も出ないじゃねえかよ」
想定していた結果のひとつとはいえ、実際に目の当たりにすると徒労感が一気に押し寄せてきた。ようやくヒントを掴めると思えば、結局また唯に振り回されたという結果だ。
かけたばかりの番号を消そうとしたところで、恵太の指は動きを止めた。唯の言葉が頭をよぎる。確か唯は、なかなか繋がらないと思うと言っていた。
『きっと恵太の知りたい答えが見えてくるから』
と言う、唯の訴えかけてくる顔。結論を出すのは、まだ早いのだろうか。恵太は小さく息をつき、スマホを脇に置いた。
十
「明後日はなんの日か知ってる?」
全ては唯が昼休みに言った、この他愛もない問いかけから始まった。明後日は土曜日、六月十七日だ。恵太は唯の思考回路を想像し、ひとつ答えを挙げる。
「分かった、なんか偉い人の誕生日だ」
唯の目が少し丸くなり、驚きを含んだ。
「おお、誕生日つながりって意味では惜しいかも。でも偉い人じゃないよ。私の誕生日」
へえ、と恵太は相づちを打つ。何と言おうか考えていると、唯が先に言葉を続けた。
「だから、私の行きたいところに付き合ってよ。今から」
「今から?」
恵太の問いに、唯はうんうん、と二度軽く頷いた。
そして、瞬く間に恵太の視界には遊園地の入り口が待ち構えている。本当に来てしまったのか、と学校を抜け出した実感が急に湧いてきた。
電車を乗り継いでニ十分ほど。観覧車があって一番近いという、それだけの理由で唯が行きたいと願った場所だ。恵太は朧気ながら、小学生の頃に家族で来た記憶を思い出す。ゴーカートに乗って両親へ手を振っていたとき以来、身近すぎて意識に上る機会もなかった。
目に入る誰しもが、社会人らしい大人ばかりなことを新鮮に感じていた。初めて見る平日の遊園地は、恵太の記憶の中の、人がひしめき合っている景色とは全く違った顔だった。園内をいくらか散策しただけで、周囲を見れば目立つのは制服の二人の方だ。
恵太は初めこそ後ろめたさを感じて早足になっていたが、だんだん大手を振って歩くようになっていた。綺麗な晴れ空に温められた園内を歩くうちに、周りのことなどどうでも良く思えてくる。よく映えた緑色の木々やジェットコースターから漏れる日差しに目を細めると、森林浴にでも来たと錯覚しそうになった。
「うわ、またジェットコースターがあるよ。乗り比べだね」
唯が一歩前に進み出て、恵太へ振り返る。待ち時間も無く乗れるものばかりなので、目ぼしいアトラクションを廻り終えるのは時間の問題だろう。恵太は呆れ声で返す。
「そんなに急いでたら、乗るもの無くなるぞ」
「そしたら二周目だね」
笑う唯は、返事も待たずに行ってしまった。
唯の後を追いかけ、唯の目に留まったアトラクションに乗るという繰り返し。恵太の足取りが重くなってくると、唯がソフトクリームを買ってあげると言う。すっかり子ども扱いになったと苦笑いし、恵太は自分でソフトクリームを買った。唯も買って、二人は白いベンチでまばらな喧噪を聞く。時々はしゃぎながら目の前を走り抜けていく子どもたちを見つけては「学校行かなくていいのかよ」と呟き、今度は自分が年寄りになった気がして笑えた。
ソフトクリームが無くなってからもしばらく、唯はあたりを見回しては、何が可笑しいのか微かに笑っている。耳を澄ませてようやく聞こえるかどうかの楽しそうな声の存在に、恵太は気づいた。それだけ聞いていたくて、自分からベンチを離れようとはしなかった。
やがて唯が立ち上がり、恵太も重い腰を上げる。
再び園内を歩き始めてからも、唯は一番目立っている遊園地のシンボルに目もくれない。観覧車に乗りたいと言って来たはずなのに、何度も乗り場の前を通りすぎた。恵太も観覧車は忘れたことにして、ゆっくり唯のあとを追い続けた。
段々周りの人が入れ替わっていき、幼い子どもや学生の姿も珍しくなくなってくる。中には一つでもたくさんアトラクションに乗りたいと、駆け足になっている人もいる。閉園時間が近いことを感じさせられても、観覧車を無視し続けた。
昔乗った記憶のあるゴーカートのコースに差し掛かり、乗るか乗らないか三度目の言い合いをして、結局乗らないと結論づけた時。唯は両手を腰に当て、辛うじて明るさを保つ空に目を細めた。
「じゃああれ、行こっか」
視線の先を追わなくとも、他に空を仰いで見上げる必要のあるものなど無い。唯が行きたいと言っていた観覧車だ。近くからだと、頂上のゴンドラはほとんど真上にあるように感じた。
「長い寄り道だったな」
「恵太も案外楽しかったでしょ?」
否定はせず、観覧車の方へ恵太が先に歩みだした。恵太の頭に、中学の卒業式の光景が浮かぶ。記憶の中で、恵太は同級生と手をつないで歩いていた。式の後に一旦クラスが解散し、卒業パーティーと称して何十人もの集団でファミレスに押し掛けるまでの間。突然、仲の良かった女子に手を引かれた。誰もが別れを惜しんだり変わらぬ関係を誓い合ったりしている中で、どうやって二人抜け出せたのかは覚えていない。誰かに見つかることを避けるように、今日という特別な日が終わらなければいいと願いを込めるように、通学路から一つ脇に入った道をただ手をつないで歩いていた。気恥ずかしさから一転、スニーカーの紐の緩みに気付き、手を離してもいいものかばかり気になり始めた頃だったと思う。その女子が「戻ろう」と言い出し、二人はどちらからともなく手を離した。それから連絡を取り合うこともなく、彼女はSNS上でアイコンが笑っているだけの存在になった。
恵太は空の右手に違和感を覚えた。初めて唯と、学校の駐輪場でした握手を思い出す。今にも手を差し伸べようと頭では思ったが、体は言うことを聞かなかった。一歩ずつ、プログラムされているかのように観覧車へ最短の道を進み、ゴンドラへと乗り込んだ。恵太は気を紛らわせるように、向かいに座った唯へ話しかけた。
「観覧車が好きとか、唯にしちゃガキ臭い趣味だよな」
ゴンドラが動き出すとともに、微かな浮力を感じて二人は窓の外を見降ろした。
「私? 観覧車は大嫌いだよ」
恵太はすぐに振り向き、唯の顔を見た。変わらない様子で、ゆっくり離れていく地面を見つめている。
「嘘だろ、わざわざ誕生日の前に、学校サボって嫌いなものに乗りに来たってのかよ」
「そういうことになるかな。乗りたくなったのはほんとだよ。でも観覧車は大嫌い」
「なんだよそれ。観覧車が嫌いってのもよく分かんねえ」
いくら見ていても唯の調子は変わらないので、恵太は唯と同じように窓の外に視線を戻した。
「観覧車ってさ、止まってくれないでしょ。一番上に着いたってさ、勝手に下がっていっちゃう」
そりゃ、上で止まられちゃ下のゴンドラはいい迷惑だろう。言いかけたが、そういう理屈ではないらしいことは恵太にも分かったので止めておいた。代わりに「すげえワガママだな」とこぼした。
「そう、ワガママなの」
唯はなぜか、正解とでも言いたげに恵太の方を振り向いた。
「だからね恵太、こんなワガママなヤツに変な気を起こしちゃダメだよ」
「変な気?」
つい裏返った声が出る。聞かなくても、意味は分かる。唯もそれを承知のようで、答えずに小さく笑った。たまらず恵太は言い返す。
「バカだなお前、よく自分で言えるなそういうこと」
今度はしっかり声を出せた。
「そう? 高校生が二人っきりで観覧車に乗ってたら、変な気になっても不思議じゃないと思ったんだけど」
「それは何の本で読んだんだ? 心理学か?」
「ううん、私がそう思っただけ。あ、すごい、けっこう車走ってるよ」
唯が園内の外周を沿うように走るゴーカートのサーキットコースを指さす。距離があるせいか、あまりスピード感は感じない。目線を広げれば、園内だけではなく近隣の住宅街や山も見下ろせる。山はまだ近くて、遊歩道や簡素な展望台も見つけられた。
「不思議じゃないの?」
「ん?」
「なんでわざわざ、学校を抜け出して今日来たか」
ああ、と心ここにあらずな返しになった。まだ、恵太の頭の中は『変な気』という言葉から逃れられていなかった。さっき唯と手をつなごうと思ったと言ったら、唯は笑ってくれるだろうか。
「明日はね、約束があるの。誕生日の日も、会うのは難しくて」
「忙しいってことだな」
急に始まった恵太には関係のない話に、興味が無いことを強調して言った。唯は動じる様子なく続ける。
「明日はね、一番大切な人と過ごす約束なんだよ」
「なんだよ、彼氏できた?」
恵太は、抑揚なく言った。自分には関係ないはずだ。そう思うとともに、こみあげる胸のざわつきを消し去れない。
「さあ。ね、最低でしょ。恵太は二番目に大切だから今日なんだよ。こんな奴のこと、もう気にしなくていいから」
「なんだよ、俺フラれてる?」
唯は俯いて首を横に振った。唯の言いたいことが理解できず、恵太は外の景色へ視線を逃すことしかできなかった。
終わりが来ないとも思えた、長い沈黙を破ったのは唯だった。
「もうすぐ一番上だね」
観覧車は音もなく回り続け、二人を高く運んでいた。地上よりも空の方が近いのではないかと思える。大切な人とやらについては、唯が言い出しておいてそれ以上話す素振りもなかった。かと言って景色を見て薄っぺらい共感でお茶を濁す気にもなれない。恵太はできるだけいつもの二人の空気に戻ることを願い、話題を探した。
「ていうかお前、なんで急に嫌いな観覧車に乗る気になったんだよ」
「今、ここで爆弾が爆発したらどうなると思う?」
求めた答えとは全く関係のない質問。不意をつかれ、文句を言うより先に答えを考えてしまう。
「どうって、死ぬだろうな。爆発で死ぬか、落ちて死ぬか」
「そこまで強い爆弾じゃなくて、煙が出るだけぐらいの感じで」
「それって発煙筒とか?」
「そうそう、それぐらい」
思いがけない方向で普段通りの会話になってきていた。唯の突飛な発想に、恵太が答える。何気なく繰り返してきた、恵太の好きな時間。
「発煙筒なら、死にはしないな。運転が止まって助けを待つぐらいにはなるかもな」
「お、恵太も私と同じ答え。というわけで」
唯は手探りで何かを探し当てようと、自分の鞄の中に手を入れた。
「お前、冗談だろ」
唯なら、発煙筒ぐらい調達するか作るぐらいはしてしまうのではないか。嫌な予感が頭を掠めて、恵太は前屈みで唯の鞄を覗き込もうとする。
「じゃん」
勢いよく上に突き上げた唯の手は、まっすぐ指があるだけで何も持ってはいなかった。
「あるわけないじゃん」
唯が無邪気に笑う。恵太は半日分の遊び疲れにも押し出され、そのまま腰が抜けたようによろける。二人掛けの椅子の、唯の横にもたれた。ゴンドラが揺れ、動きを小さくしようと努める。
「お前が言うと冗談に聞こえないんだよ」
「本当は止めてやろうと思ったんだけどね。一番高いところで。それが、今日観覧車に乗りたかった理由」
唯は冗談とも本気ともつかない、微笑みを浮かべたままだった。
「ドラマとかでさ、このまま時間が止まればいいのに、なんてよく言うでしょ。私はそれが今思ってることだよ」
隣り合って座ったからだろうか。言葉を失くした数秒が、今までよりも逃げ場のない沈黙を主張する。恵太はちぐはぐな頭でなんとか言葉だけ繋げた。
「明日、一番大切な人と会うくせに何言ってんだよ」
「ほんと、そうだよね」
恵太は否定してほしかったという、自分の淡い期待の存在を知った。どういうわけだか唯も浮かない様子で、小さな鼻が微かに鳴ったと思った。
「やっぱり観覧車は嫌いだな。全然止まってくれない」
「当たり前だろ。ここで止まったら下の人たち可哀そうだし。帰りはどうすんだよ」
さっきは飲み込めた言葉を、今度は言ってしまった。唯が訳の分からないことばかり話すせいだ、ということにしておきたかった。唯も今度は、はっきり恵太に聞こえる大きさで鼻を鳴らした。唯の不満を嘲笑うように、ゴンドラはいつの間にか頂上を過ぎて下りに入っていた。
「知ってたんだけどさ。止められないって。これ以上恵太に迷惑かけられないし」
恨めしそうに唯は外の景色を見た。恵太も同じように、反対側の窓に目をやる。言葉を失くすと、沈黙とともにまたあのざわつきを感じずにはいられなくなる。唯が明日会うというのは、どんな相手なのだろうか。唯は、なぜわざわざそのことを、こんな意味ありげな場所で自分に話すのだろうか。延々続く街並みの端に見える空と地の境も、立ち並ぶビル群も思っていたよりも広く見える園内も、恵太の脳裏には何も与えてくれなかった。
恵太の物思いを止めたのは、すぐ隣からする嗚咽を噛み殺すような声だった。
「唯?」
いつの間にか、唯の横顔に大粒の涙が溜まっているのが分かった。声をかける間もなく、頬をすべり落ちていく。
「馬鹿だよね。知ってたのに、何がしたかったんだろう」
唯の声の震えがどんどん強くなっていくことが分かる。声だけではない。まるで凍えるように、肩も震わせ身を固くした。
「どうしたんだよ。俺がつまんないこと言ったせいか?」
訳も分からず、恵太は泣きかけの赤子と対峙したように慌てふためく。唯はすかさず首を横に振った。
「優しいよね、恵太は」
と掠れた声で言うと、「これは私がワガママだから泣いてるだけだよ」と続け笑顔を作った。唯の目がくしゃっと形を変えると、また大きな涙が落ちる。
「生け贄の話なんだけどさ」
息を吸い込み、唐突に発せられた唯の言葉が、恵太には一瞬うまく認識できなかった。思い直し、唯が恵太と竜海に課した生け贄という役目のことだと分かった。
「ごめんね、めんどくさいでしょ」
「今更だし、どうしたんだよ」
今になっても、何が生け贄なのか恵太も恐らく竜海も見当がつかないままだ。幽霊にかかるという電話番号も、何度か試したが音沙汰は無い。ただ、まとわりついて離れなかった疑問も、この場で重要なこととは思えなかった。
「ごめん」
今度は恵太に向き直り、項垂れ、また涙を落した。唯のスカートに粒が落ち、染み込んでいく。
歯痒さを、恵太は両の拳に込め握りしめた。唯は大事なことはいつも隠している。自分だけ分かったような口を利いて、人を振り回して、今度は何に謝られているのかも分からないままに謝られて。それでも恵太は、唯の涙が止められるのなら、肩を抱き寄せたいと思う。手を握りたいと思う。これが唯の言う『生け贄』の行く末ならば、大した趣味の悪い遊びだ。また笑って話せるようになったら、どれだけ時間がかかってでも、いつかきっちり説明してもらおうと心に決めた。
下り終えた観覧車は、無言の二人を追い出すように扉を開いた。電車に乗って、二人並んでそこにいるだけの帰り道。観覧車の続きのように、二人掛けの席に座っていた。窓の外を走る空は、恵太の予想に反して夕暮れが訪れる気配もない。恵太と唯は交互に口を開いては、遊園地の感想も、吊革広告から見つけた話題も途絶えさせ消費していく。
「いい加減もう普通に戻ろうぜ」
唯が返事の代わりに、ゆっくり恵太の方を振り返る。すべて元通りになる魔法の言葉を探して、恵太は口を開いた。
「いいよ」
唯は、不思議そうな視線を恵太の目から離そうとはしない。
「許すよ。何に謝ってんのかもしらねえけど。お前が謝ってることも、生け贄の件も全部。だから、謝るとかめんどくせえこと考えるの、やめろよ」
電車が止まって、乗客が入れ替わる。降りる人が次第に増えて、一駅ごとに空席が増えているようだった。唯が降りる駅まであと七駅か八駅だったろうか。黙ったままの唯は、人を吐き出し終え扉が閉まったのを合図にしたように、「うん」と呟いた。
「ごめんね」
「だから、謝るなって言ってるだろ」
「うん、今ので最後」
目を合わせて笑った。恵太は張りつめていたものがふっと緩むのを感じた。
「許してもらうついでに、もう一つだけお願いしていい?」
「無謀なやつじゃなきゃな」
唯は小さく吹き出しそうになってこらえた様子だった。何が面白いのか、聞いても教えてもらえない気がして気づかないふりをした。
「やっぱりやめた。家まで送ってもらおうかなって思ったんだけど、もう十分付き合ってもらったし」
「なんだそれ」
唯の家は、確か駅から降りてそれほど歩かないと聞いたことがある。送るぐらい、造作もないことだと思ったがそれ以上唯が言わなかったので恵太も触れなかった。唯が遊園地のことを話し始めると、今度は思い出したように、いつもの二人の掛け合いが止まらなくなる。
七つ目の駅で立ち上がり、「バイバイ」と振り返る唯を見送った。空いたままの隣の席を見つめながら、まだしていないアトラクションの話があったことに気づく。唯が観覧車を嫌いと言った理由が、今なら少し分かる気がすると恵太は思った。
十一
始めは遠慮がちだった話し声が、教室中に散在していき、競い合うように大きくなっていくまで時間はかからなかった。恵太は騒音にしか思えず顔をしかめる。本来なら一限目が始まってから二十分は経っている時間だが、担当教師がやって来ないのだ。席を離れる者もおり、教室を出ないという申し訳程度の決め事以外は存在しなくなっている。教室に唯の姿はない。恵太は普段なら星井あたりのグループに混ざっていくのだが、今はスマホの画面以外の情報は頭に入ってこないよう努めた。味方のキャラクターがアニメ絵のモンスターを倒していくよう、画面を叩くことで導く。ほとんど意識は画面に向いておらず、半自動的に指を動かすだけで成立していた。
手に伝わる振動より先に、画面に割り込む枠に気づく。誰かからメッセージが届いた知らせだ。唯のことが頭に浮かび、中身を確かめようとしたが、竜海からだと分かって手が止まった。
唯とは、三日前に電車で別れてから連絡がとれていない。大切な人と会うという話が気になりながらも、男友達という立場には何の問題もないと思い、一応誕生日祝いのメッセージを送った。恵太自身でもなんと送ったか思い出せないほど簡素なメッセージだが、返信がないのは予想外だった。後になって考えれば考えるほど、やはり観覧車でのあれはフラれたということに思えてくる。といっても付き合っているわけでも告白したわけでも、恋愛対象なのかも曖昧なのだ。別れ話でも絶縁宣言でもなく、なんと呼べばいい状態なのかよく分からない。竜海に話してみるぐらいしか、この靄を払うアイディアは出てこないと腹を括り、竜海のアイコンに触れようとした時だった。教室の前の扉が開き、反射的に誰もが顔を上げる。喧噪が静まるまでの早さが、その相手の意外さを物語っていた。確か国語の増田という教師だったと思うが、恵太たちのクラスは別の教師が担当している。そもそも、一限目は英語のはずだった。席を離れていた生徒も、おずおずと身を低くして席へ戻る。彼女が現れた意味を、誰もが図りかねていた。教室中の視線を集めて、増田が口を開く。
「おはようございます。授業の時間ですが、皆さんに辛いお知らせをしなければなりません」
渋みのある声と神妙な面持ちが、無言のメッセージとなって生徒たちに緊張が伝播していく。恵太もその波に飲まれつつ、増田が学年主任であることを思い出した。
「一昨日のことですが」
増田は言いにくそうに短く沈黙し、唇をかみしめた。事態の深刻さだけが先に伝わってくる。それでも、次に増田が言った言葉は到底、心の準備程度で足りるものではなかった。
「小川唯さんが亡くなりました」
そこから先の言葉を、恵太はよく覚えていない。
第二章
一
初めて見る唯の父親は、温厚で物静かにみえる色白の中年だった。恵太は自分の両親と比べて随分若い気がしたが、丸みを帯びた頬と背中から、見た目よりも歳を重ねているのかもしれないと気付いた。あるいは、唯も少し丸みを帯びた頬をしていたのでそういう輪郭の家系なのだろうか。喪服のせいもあるのか、温厚な中にもどこか神経質そうな近寄りがたさを感じる。数多の供花についた札や、聞くともなく耳に入ってくる話から、大学の准教授をしていると知った。唯の父親らしい、と思い恵太は妙に腑に落ちた。
唯の父親が立ち上がり、方々に頭を下げる。嫌でもこれが葬儀という儀式の場だと分からせてくる線香の匂いの中、喪主である唯の父、小川彰高の挨拶が始まった。表情の一つも変えず、動かし方を忘れたような顔で彰高は話している。急に家族を亡くした時、相場は涙で言葉が出なかったり、立っていられなくなってしまったりするものではないかと思っていたが、彰高は何の感情も宿さない声をしていた。原稿を読んでいるのかと思って手元を見たが、何も持たず体の前で両手を組み合わせている。ほとんど内容が頭に入ってこない中で、辛うじて恵太が把握できたのは、唯の母親は唯が中学生の頃に亡くなっていること、それと、彰高と唯の思い出話がいくつか。若くして妻と娘に先立たれたことになる彰高は、その境遇とは不似合いな平静さで、見ている方が異様に感じるほどだ。もう一つ、恵太が異様に感じたのは唯が死んだ理由を示す言葉が出てこないことだった。
増田が教室で唯の死を報せたとき、死因については「はっきりしたことは分からない」の一点張りだった。それが却って憶測を膨らませる事態になりかけたからか、その日のうちに再度説明が行われた。唯の死因は、自殺だと。それから返ってくるはずもないメッセージを唯に送ったり、唯の姿を探してみたりしてどうやら嘘ではないらしいと感じ始めたところでの葬儀だ。
恵太にとって、葬儀は初めての経験だった。幸いなことに祖父も祖母も、いつかは亡くなってしまうのだと思わせたことすらない健在ぶりで、死は漫画やドラマの中でしか接したことがない。いつかはあの元気な祖父母とも別れの時が来るのかと、祖父母の葬儀を想像しかけていることに気づき考えるのを止めた。
家を出る時に、険しい顔の母親が念入りにシワやほこりをチェックするものだから、いつも着ている制服のシャツすら体に馴染めていない気がする。隣で竜海が、ポツポツと自分たちがするべき段取りを説明してくれなかったら、心細くて周りを見るどころではなかったかもしれない。
「じいさんが亡くなった時はそんな感じだったな。とりあえず、前の人に付いていけば大丈夫だと思う、多分」
経験があるとはいえ、口ぶりからすると拠り所はその記憶だけなのだろう。遠い記憶を確かめるように頷き、竜海が言った。最近になってぴんぴん飛び跳ねさせるようになった髪が、今日は自然におろして分け目だけ作った形になっている。営業サラリーマン一年目。と恵太は思ったが口にするのは葬儀が終わってからにしておくことにした。
自分たちのすべきことは当面、椅子に座って神妙にしておくことらしい。そう悟って恵太は周りの様子を窺った。恵太たちが着いた時はまだ席に空きが目立ち、周囲を恐る恐る見回しながら来賓側のやや後ろの席にしたのだった。それが気づけば、ほとんどが黒色で埋まっている。学制服の数からして、クラスメイト達も全員集まったぐらいだろうか。ほぼ全員が、竜海と違って普段の見慣れた髪型そのままだった。恵太は自分が少数派でないと知って安心した。
会場の中は、学校関係者や担任の呼びかけで全員来ていると思われるクラスメイトで八割方埋まっているようだった。あとは、親族と思われる大人が数人といったところか。唯は高校になってから引っ越してきたから、付き合いは学校内でのものがほとんどだったようだ。
意味もないのに振り向くと、後ろのあまり親しくない女子と目が合ったので慌てて前に向き直った。所在なく目を伏せる。
恵太は物憂げに息を吐いた。通夜や葬式というものは誰が考え出したものなのだろう。なんの法律があるわけでもないのに、わずかでもこの空気からはみ出ると場を乱してしまう気がする。微動だにせず前を見据えたままの竜海を横目で見た。
「なんか、重いな」
「当たり前だろ。葬式だぞ」
竜海は眉だけひそめ、視線を動かさず答えた。
「そうなんだけど。もっとこう、ラフに死者を見送る会とかダメなのかな。その方が死んだ奴も嬉しいっていうか」
そこまで言ったところで竜海に横から腿を小突かれ、目配せされた。声に出さず、口だけ『おい』と動いている。恵太としては周りに聞こえないよう十分声を落としていたつもりだったが、それでも竜海はこの場に相応しくないと感じたのだろう。
「でもまあ」
反省して口を閉じた恵太に向け、意外にも竜海は言葉を続けた。
「唯はその方が喜ぶかもな」
返事の代わりに微かに頷いて、恵太はまた目を伏せる。唯が何を考えているかなど分からないが、きっとそうだろうと恵太も思う。同時に、『考えている』と現在形で唯のことを捉えている自分の鈍さに驚いた。それだけではない。唯が死んだにも関わらず、この自分の変わらなさはなんなのだろうか。悲しいような、寂しいような気はするがそれだけだ。本当にそれでいいのか、何か大切なことに気づいていないんじゃないか。そんな、よく分からない焦りのようなものは感じるがそれより先に感情は進まなかった。ただ、恵太がどう感じようが事実は変わらない。唯は死んだ。自らの手で命を絶ったのだ。
なぜ? 竜海も、クラスの連中も、教師も、もしかしたら親族も、その疑問に答えられる者はいないのではないか。唯に何か死ぬ理由があったか?
本当は、増田から報せを聞いたときすぐにでも竜海に疑問をぶつけたかった。竜海でなければクラスの誰かでもいい。誰でもいいから、そんな理由があるなら教えて欲しかった。
疑問を口にできずにいるのは、怖いからなのかもしれない。自分は唯と、誰よりも一緒にいたつもりだ。理解できない行動も多かったが、それでも他の誰かよりは唯のことを分かっているつもりだった。それがあっさり誰かに答えられてしまったらと思うと、怖い気もする。
『知らなかったの? 小川さんはずっと死ぬほど悩んでたのに』
そんな答えを耳にしたとき、自分は何を思うだろう。あるいは、いまいち唯の死を悲しむことができていない気がする自分は、一番の理解者なんかじゃないのか。唯が死ぬ直前に言っていた、大切な誰かなら分かるのか。
考えを巡らせ固まっている恵太が我に返ったのは、前の方から若い女の慌てる声がした時だった。喪服の大人たちが何人か、一か所に駆け寄っていく。クラスの女子が立ち上がれずに崩れ落ちてしまったらしい。学生グループの先頭に立って行こうとした、級長のようだった。
それを見て恵太は、葬儀がいつの間にやら焼香まで進んでいたらしいと知った。やり方はさっき、竜海が教えてくれたので大丈夫、のはずだ。
崩れ落ちた級長は、クラスメイトに肩を抱かれ席に戻るか尋ねられていたが、制して焼香の列に並んでいく。
『本気でそんなに悲しいか?』
言いかけて今度こそ、恵太は押しとどまった。さすがにそんな言葉を耳にしたら、誰もが気を悪くするだろう。
級長の一件以外、焼香の列は滞りなく進んだ。恵太も列に加わり並んだところで初めて、前列の方では女子の一団の誰しもが涙していることを知った。不思議な光景と、不思議な感情だった。級長も含めクラスメイトの誰一人として、唯と親しくしているところを見たことがない。押し込めたばかりの『そんなに悲しいか?』という感想が、また口から出そうになっていた。次第に胸の奥底から、微かな苛立ちが湧いてくる。悪意たっぷりに『お前ら、死ぬまでなんとも思っていなかったくせに』と言ってしまって、この感傷的な空気を台無しにしてやりたくなる。
ただ、それは思いつき程度のものだ。恵太は容易に切り替えて、祭壇の前に立つ。竜海に言われたとおり、遺族に向けてぎこちなく頭を下げた。体を向けて顔を上げ、反対側に向き直るまでの一瞬だが、恵太はどこを見ていいのか迷った。若い家族に先立たれた肉親。特に涙も流していない自分は、泣き崩れ嗚咽を漏らす人もいるだろう方向へ顔を向ける自信がなかった。後ろ暗い気がして、ほとんど遺族側は見ずに焼香台と遺影に向き直る。遺影など見ても、ただの写真であってそれ以上でも以下でもない。今更、唯の顔を写した紙を見ることに意味など見出せなかった。
恵太の思いとは裏腹に、人間というものは無意識のうちに人の目に惹きつけられてしまうらしい。自分の焼香の番が終わり、肩の力が抜けた瞬間に遺影と目が合っていた。なんということはない、よく知っている唯の顔だ。やはり特別なものではなかった。特別なものになってしまったのは、目を見開いて、瞬きをして、恵太をからかって呑気に笑う唯だ。葬儀前に火葬されて骨になってしまったという唯は、もう紙の上でしか笑わない。いちいち気が付くことが当たり前のことすぎて、頭の中がぐちゃぐちゃだ。
恵太は元の席に戻ると、体全身を椅子に預けて宙を仰いだ。葬式に似つかわしくない、まるで公園のベンチに座る酔っぱらった中年のような恰好だ。もうどうなってしまってもいい、そんな気がして特大のため息に意思を込めた。
「大丈夫か?」
竜海が顔をまじまじと見てくる。恵太は嘘をつくのも煩わしく、
「なんかもう、死にたくなってきた」
と答えた。窘められるだろうと予想したうえでの返事であり、竜海が口を開く前に姿勢を正そうとした。
「まあ、そうかもな」
何が伝わったのか分からないが、竜海は口元だけで呟き、残りわずかとなった焼香の列へと視線をやっている。恵太は拍子抜けして、ゆっくり姿勢を正した後に今度は無意識のため息をつく。
終わったら、竜海には唯が死んだ理由について心当たりがあるか聞いてみようか。もし何も知らなかったとしても、二人で考えれば何か新しい発想に行き着くかもしれない。それでも何も出てこなかったら? 何かできることがあるのだろうか。そこまで考え、恵太は思い直した。違う。何か出てきたとしても、自分にできることはもう何も無いのだったと。
二
竜海に唯が死ぬ理由に心当たりがあるか聞いてみたが、あっさり首を振られてしまった。家に着き、どこにいて何をするのか正解か分からなくて、結局恵太は自分のベッドの上で天井を見つめた。スマホを両手で掲げて操作してみるが、何も頭に入ってこない。手が重たくなってきて、体の横へ両手とも投げ出した。視界から画面が消えると、なんの救いにもならないと思っていた行為が、思考を食い止めるのに役立っていたのだと知らされる。もう何度目か分からない、自問自答がまた浮かんでくる。
唯が自殺するまで追い詰められた原因は、誰にも分からないのかもしれない。結局、唯にとって自分はなんだったのだろう。死にたいほど悩んでいたとして、『二番目に大切な人』にはそれを相談する価値もなかったのだろうか。『一番大切な人』には相談したのだろうか。どうして、そいつは止めてやれなかったのだろう。
考えたって分かりようがないという結論に至ると、今度は唯と過ごした記憶が頭に流れ込んでくる。初めて会った時のこと、何気ない会話、時にイラつかされたこと。やたら本が好きで、いつも鞄がパンクしそうだったこと。いつからか、暗い顔をしている姿を見るようになったこと。
一瞬、ひと際様子のおかしい唯の姿がよぎる。あれはいつだったか。目の前で、途端に唯の様子が一変した日。恵太はすぐに、その光景の正体に思い当たった。莉花という女と会った時だ。ヘイトロッカの後追い自殺についてインタビューの最中、唯は続きができないほど蒼白になった。莉花と約束したインタビューの続きは、叶わないものになってしまったのだと、また当たり前のことに気づかされた。
後追い自殺。その響きに、恵太は惹きつけられた。好きなバンドのメンバーが死んだからといって、後を追って死ぬファンが何人もいた。友人が死んだ時、後を追うことは不自然なことなのだろうか。世間が思うより遥かに、大切な相手がいない世界を無理に生き続ける必要はないのかもしれない。
「ばかじゃねえの」
恵太は声にならない、微かな呟きで自分に言い聞かせた。振り切るように体を起こし、ベッドから足を下ろす。
あまりにも浅はかで無意味だと、考えるまでもなく分かることだった。分かると同時に、答えが出たはずの疑問がまた顔を出す。では、自分はどうしたらいい?
無限に続く螺旋に落ちていきそうだった。逃れる術を探して部屋の中を見渡したが、結局手元にあるはずのスマホを手探りで求めた。
画面上に電話帳を呼び出し、未だ正体の分からない電話番号に触れる。唯が残した、幽霊と繋がるという番号だ。唯が死ぬ前にも何度かかけてみたが予想を裏切る事態は起きず、聞き飽きたコール音と留守電の自動応答アナウンスが流れるだけだった。
ほとんど自動的な動作で通話マークを押す。初めて押したときのような躊躇いは、すっかり無くなっていた。ほどなくして留守電の応答に切り替わる。不思議と、番号を削除しようという気にはならなかった。
三
あまり喫茶店というものに縁がない恵太は、ファミレスの倍近くするドリンクに戸惑いながらもコーラを注文した。唯なら、見慣れない名前のジュースや紅茶にするんだろう。唯ではなく向かいに座る竜海は、飲み慣れないコーヒーを頼んでみると息巻いている。
竜海から飯でも行こうと声をかけられた時は、自分でも想像していないほど身が軽くなった気がした。竜海と二人で会うのはいつ以来だろうか、と思い出すと唯にすっぽかされたカラオケが最後だった。唯が死んだと知ってから最初の土曜日の今日に至るまで。何を考えても唯に辿り着くので、唯のことを考えないのは無理だという結論に恵太は達していた。
気を紛らわせるように周囲に目をやる。店内の壁紙はほとんど水色で統一されていた。恵太たちが座る席も、台は薄い木目調だが椅子の淵の木製部分は水色で塗装されている。頭上にはテーブル毎に笠が着いたランプが吊るされており、優しい黄色で照らされる。竜海が指定した喫茶店だが、恵太は自分たちには不相応なのではと不安になった。
禁煙席と喫煙席は完全に別れているので喫煙席がどのぐらいの広さか分からないが、禁煙席はテーブルが八つある。恵太たちの他には大学生ぐらいに見える女の二人組と、夫婦らしい五十代ぐらいの男女がいるだけだった。見えるところに店員の姿がない。竜海が喫煙席との間にあるカウンターへ呼びかけると、若い茶髪の女店員がやって来て、テーブルの上のベルを鳴らしていいと笑顔で言う。恵太と竜海はなんとか取り繕って注文を終えることに成功したが、店員が去った後に急激な気恥ずかしさに見舞われた。
「なんでこの店なんだよ」
まだ後ろ姿のある店員に聞こえないよう、恵太は控えめに尋ねた。
「一度来てみたいって前から思ってたんだよ」
「違うだろ」
竜海の答えに、恵太は異を唱えた。外食といえば牛丼かラーメンかハンバーガーが持論の男が、そんな動機には辿り着かないだろう。竜海が選んだ理由は、恵太には明らかだった。ここは、唯がよく話していたお気に入りの喫茶店だ。
「唯が来てた喫茶店だからだろ。どうでもいい嘘つくなよ」
「そりゃそうだ。意味ない嘘だな」
「だからなんで、唯が来てた店に来るんだよ」
恵太と竜海が小さくもめていると、店員がドリンクを運んできたので二人とも会話を止めた。竜海がテーブルの脇に置いてあった小瓶を取り、蓋の中を見る。茶色い砂糖を難しそうな顔で眺めてから元の場所に戻し、ブラックのままのコーヒーを啜っている。
「親に聞いたんだよ。誰かが死んだとき、どうやって気持ちを落ち着かせるんだってな。そしたら、その人が好きだった場所を巡ってみたらどうだ、だと。そうしてると、なんか頭の中が整理されていくんだってよ。よく分からん理屈だけど」
「お前、結構落ち込んでるんだな」
恵太が意外そうに正直な感想を呟くと、竜海はわざとらしくこけるような仕草をして恵太を見た。
「そりゃそうだろ。お前ほどじゃないけどな」
「俺? 落ち込んでるか?」
「だいぶ。返信の遅さだけでも今までと違うって分かるぞ」
「お前、なんかキャッチャー系男子っていうよりオカンって感じだな」
ようやく二人は少し笑えた。竜海がコーヒーを飲んでいる姿の似合わなさも、恵太には可笑しさに拍車をかけて感じられた。
「なあ、やっぱり唯が死ぬ理由に心当たりないのか?」
葬儀後にも一度した質問だが、恵太は確かめずにいられなかった。
「ああ、全くない」
竜海の答えには、一度目と同じく迷いがなかった。恐らく、竜海も何度も反芻して出した結論に違いないのだろう。恵太としては予想していた答えとはいえ、残念なような安心したような、複雑な気分だった。
「むしろ恵太が知らないなら、誰にも分かりようがないんじゃないか」
「いや」
言いかけて、恵太は続きを飲み込んだ。唯が遊園地で言っていた『大切な人』のことを言おうとしたが、唯が秘密にしていたかもしれないと思うと気が引けた。
「いや、もしかしたら学校の連中とか、探せば一人ぐらい何か知ってる奴が出てくるかもしれないだろ。お前の周りで何か聞かないか? また変な噂レベルとかでも、なんでもいい」
なんとか不自然じゃないように言い繕った。竜海は疑問に感じる様子はなく、知っている情報を絞り出そうと頭を捻らせている。しばらく考えてから、口を開いた。
「すまん、あんまりいい噂じゃなきゃ聞いたが」
また身勝手な噂をしている奴らがいるのか。恵太は自分で聞いておきながら、唾でも吐きつけてやりたい気になってくる。顔には出さないよう、頷いて続きを促した。
「と言っても、くだらなさすぎて何の参考にもならないと思うがな。唯がその、ヤバイ連中とつるんでて、それで殺されたんじゃないかって噂だ」
「マジでくだらないな。小学生が作った話か?」
恵太は鼻で笑ったが、竜海は真顔のままだった。
「それが一応、根拠はあるらしくてな。桜町通りで夜にフラフラ歩き回ってるのを見たヤツがいるんだと。まともに歩けてなくて、クスリでもやってるんじゃないかって」
桜町通りというロケーションが唐突すぎて、漫画の話にさえ思えた。平和に暮らしている高校生には無縁の歓楽街だ。クスリという安直な登場人物。ここまでくると噂というよりも、デマ以外の何でもないだろうと呆れたくなる。
「そんな話、信じるやついるか?」
笑って同意してくれる竜海を期待したが、曖昧な言葉が返ってくるだけだった。まことしやかな話として竜海に届いたことは、恵太にも想像できた。
「結局何も分からないってことだな」
恵太はうなだれ、授業中のように机に突っ伏した。
「なんかもう、死にたくなってくるな」
「おい」
竜海が肩を揺すり、周りを見るよう目で訴えてくる。構わず、揺すられるまま居直った。
「こちら、試作品のサービスです」
頭上からするウェイトレスの声に驚き、恵太は渋々体を起こした。テーブルの上に並べられた小皿に、一口サイズにカットされたムースが乗っている。
「ほら、生きてりゃいいことあるだろ」
竜海は添えられたティースプーンを手に取り、恵太にも食べるよう促した。
「こんなんで喜べねえっての」
「なあ恵太」
「なんだよ」
竜海の改まった声に顔を向ける。
「死ぬなよ」
「は?」
「今の恵太に死にたいとか言われると、ガチっぽいんだよ。唯が死んでそりゃヘコむだろうけど、暗すぎて心配になるわ」
「マジでとるなよ。唯が死んだからって、俺が後追って死ぬようなことあるわけないだろ」
竜海はティースプーンにムースを乗せると、味わう様子もなく一口で飲み込んだ。
「唯が死んだのもよく分からないんだぞ。俺からすりゃ、恵太が突然死んでも不思議じゃないって考えるんだよ」
「お前の方が暗いよ」
吐き捨てるように言ったが、竜海の言うことが真っ当なのは分かる。自分の考えよりも反発した態度になってしまった気がして、恵太は口ごもった。
「そうだな、確かに俺が暗いのかもな」
意図せず竜海が苦笑いし、視線を外した。恵太はムースを必要以上に細かく切って食べ沈黙をごまかしていたが、すぐに無くなってしまった。
「ところでお前、どっちがタイプ?」
竜海が前かがみになり、耳元で聞いてくる。
「なんのことだよ」
「ここの店員のことだろ、当然」
店員に気づかれないようにするためか、竜海は顔は動かさず、目線だけでカウンターの方へ注目を促す。カウンターは禁煙席エリアを出てすぐのところにあるが、二人のいる位置からではトイレへ向かう通路があって見えない。
「見えねえ。つーかどっちって誰のことだよ」
「さっき顔見ただろ。最初に来た茶髪の子も、デザート持ってきてくれた眼鏡の子も二人とも可愛いぞ」
さっきまでの神妙な顔つきはどこへやら、竜海は楽しげに横目でカウンターに注目している。店員が出入りするときに、姿が見えないか窺っているらしい。恵太は店員の顔を思い出そうとはしてみたが全く印象がなかった。
反応が物足りないのか、竜海は恵太の肩を叩き、無理やり会話に参加するよう促した。
「俺が言いたいのはな。世の中にはまだたくさんいいことがあって、かわいい子もいるってことだ」
ようやく竜海の意図したところが分かった。竜海なりに、明るい方へ話題を向けたかったらしい。
「そういう話な。下手くそなんだよ、竜海は」
「ああ、悪かったな下手くそで」
竜海が肩をすくめ、自嘲気味に笑った。恵太も同調し、「悪いな」と今できる精いっぱいの謝辞を告げた。竜海が手のひらを見せ「気にすんな」と頷く。
恵太は、竜海の親が教えてくれたという『死んだ人の好きだった場所へ行く』という視点で再度店内を見渡す。唯が好んだのは、この店の淡い色調なのだろうか。それとも、気に入ったメニューでもあったのか。メニュー表を見てみても、見当もつかない。分かるのは、高校生の小遣いで常連になるには、かなりハードルが高い値段設定ということぐらいだ。バイトをしていたという話は聞いたことがないが、父親が大学の准教授だとやはり金にも困らないのだろうか。恵太はそんな思いを、竜海にぽつりぽつりと話し始めた。こんな無駄話が、『思いを整理する』ということになるのだろうか。分からなくとも唯についての話が尽きることはなく、恵太はそれが心地いい気がした。
四
学生服の波をかき分け、一歩でも早く進みたかった。駆け出したくても昼休みの売店前は、校舎への入り口の幅全てを使って人が並んでいる。恵太は人波の先に消えつつある後ろ姿の、行くあてを見失わないようにだけ心がけた。目印にしていた跳ねた茶髪の襟足と、丈の短いスカートが校舎内の階段を上がって行き視界から消える。と同時に行列の間を縫うことに成功し、恵太は自由になった体で階段へと急いだ。
追いかけながら先ほど見た光景の意味を考えるが、答えは見出せない。あのヘイトロッカの件で会って以来、初めて莉花の姿を見かけたのだ。だが恵太が気になっているのは、莉花自身よりも莉花が手にしていた物だ。なぜそれを莉花が持っているのか、直接話して確かめずにはいられなかった。
二階に上がると、上の階へ続く階段も目に入る。迷ったが、二年生の教室が多い二階にいる可能性に賭け、そのまま廊下を彷徨った。
莉花は同じ二年生ということは聞いていたが、クラスまでは聞いていない。一つずつ教室の中を窺いながら、廊下にいる生徒にも目を光らせた。今見つけないと、また偶然見かけるのを待つことになってしまう。一か月経って初めて見かけたことを考えると、この機会を逃したくなかった。だが、廊下の突き当りに着いても莉花の姿は無い。
三階にも数は少ないが二年生のクラスはある。三階に行こうと、来た道を戻り始めてすぐのところで恵太は違和感に気づいた。女子トイレから出てきた人影が、すぐにトイレの中に引き返したのだ。一瞬だが、背格好が莉花に似ていた気がする。恵太が目をやった瞬間に引っ込んだのも、なおのこと意味ありげに見えた。
考えた挙句、恵太は廊下の壁の張り出した部分に隠れ、様子を見ることにした。隠れるといっても横や後ろからは丸見えなので、傍から見てかなり不審なのは承知の上だ。誰に言い訳をするでもなく、待ち合わせでもしているかのように時々辺りを見回してみたりする。数人を見送った後、トイレから辺りを窺いながら出る横顔があった。莉花だ。すぐには出てこず、何かを警戒するように二度三度と左右を確認している。恵太は一旦陰に隠れ、莉花が自分を警戒していることを確信した。恐らく、恵太が売店で莉花の後を追おうとした時から気づいていたのだろう。だが、莉花に警戒されないといけないような覚えはない。戸惑いながらも、再度トイレに退避されては事が進まないので、莉花がトイレから離れたところで声をかけることにした。
周りに恵太の姿が見えないことを確認したからだろうか、莉花が廊下へ出て来る。ちょうど、恵太がいる方へ向かってくるのが分かった。正面から見る莉花は、学校の外で初めて見た時とは違った印象だった。インタビューの時は独特の出で立ちで近寄りがたさがあったが、制服の今は違った威圧感がある。腕組みに眉間に皺を寄せて歩く様は、体全体で不機嫌を表していた。
必要以上に驚かさないよう、恵太は近づいてくる莉花との距離にまだ余裕があるところで顔を見せることにした。心の中でカウントダウンし、ゆっくり一歩踏み出す。莉花はあと五メートルほどのところに来ていた。恵太と目が合って、明らかに表情が引きつっている。それには触れず、恵太はごく自然な声を心がけた。
「久しぶり」
小さく手を振ってみせる。莉花は腕組みしていた手を腰に当て、舌打ちが聞こえてきそうな顔で目を逸らした。
「ごめん、来ないでくれる」
言われた通り、恵太は足を止めた。これ以上近づくと、今にも振り返って駆け出してしまいそうだ。改めて感じるのは、警戒というより拒絶に近い意思だ。どちらにしても、恵太には身に覚えがない。
「どうしたんだよ。俺が何かしたか?」
莉花から答えは無い。廊下の隅に視線を落とし、身を固くしたままだ。通り過ぎる学生らによって、恵太と莉花の周囲に境界線が作られた。見えない境界線の外から、遠巻きに何事かという視線を感じる。莉花が話に応じる気がないのなら、本題を早く切り出してしまわないと良くないことになりそうだ。
「スマホに着けてるストラップ、見せてくれねえ?」
「何それ。なんで見せなきゃいけないの」
恵太は何歩か進み出た。対峙する莉花に近づいていくと、以前会った時と印象が違う理由の一つに気が付いた。ほとんどメイクをしていないようだ。目元や頬の色白さに青みがかかっており、疲れでくすんでいるかのように見えた。莉花が一歩後ろに引いたので、恵太も立ち止まる。
「それ、唯のストラップと一緒なんだよ」
視線を上げる莉花と目が合った。強張った顔のまま、微かに口元が動いたかと思ったが返答はない。スマホを見せようとしないことが、図星だったと確信させる。手から垂れ下がる、赤いピエロ。いつも唯と共にあった光景。なぜかそれが、壁にもたれてスマホをいじる莉花の手にあるのを見つけ、追いかけて来たのだ。他では見かけたことのない代物だ。偶然というのは考えづらい。
「見間違いでしょ。お願いだから、私に関わらないで」
突き放すような早口のあと、莉花は一旦言い淀んでから言葉を続けた。段々感情がこもって、声が大きくなる。
「唯は死んじゃったんでしょ? ならインタビューのこともナシだよね。私は、あの子から誘われて会いに行っただけなんだから」
ヒステリックに言い終わるなり、恵太の反応も待たずに踵を返して去ろうとする。追いかけたくとも、通りすがりから浴びる注目が、莉花の突き刺すような声でより強くなってしまっていた。躊躇ったが、なんとか足を進めて莉花の肩に手を伸ばした。
「待てって」
肩に手を触れたかどうかというところで、莉花が振り返って睨みつけてくる。
「あんたには関係ないでしょ。いい加減にして」
伸ばしかけていた手は、莉花に乱雑に振り払われた。何がこれだけの剣幕を呼び起こさせるのか、想像がつかない。去っていく後ろ姿を、今度は追うことができなかった。
五
恵太はこの数日、部屋に着くと鞄を机に置いたまま、ベッドに腰かけて過ごすようになっていた。服を着替えるでも、鞄を開くでもなくただ座る。母親に小言を言われることもあるが、風呂に入る時に着替えればいいと思うと、改める気にもならなかった。そうしていると、頭の中にこの何日かの出来事がフラッシュバックする。考えたくないときはスマホで画面を捲る。この繰り返しだった。
今日フラッシュバックするのは、不可解さに他ならない。莉花のスマホに付いていた、唯のストラップ。インタビューの時とは別人のような莉花の態度。
「あー」
唸って、次に浮かんでいた言葉を飲み込んだ。『死にたい』と口に出しかけたが、竜海に窘められた時のことが浮かんだのだ。「死ぬなよ」と言う竜海の真顔。当たり前だ、本気で死ぬわけはない。なのに、浮かんでくる思考を止められない。唯の死ですでに理解が追い付いていないのに、また分からないことが出てくる。考えても考えても終わりが見えてこない。もう誰でもいいから息の根を止めて解放してくれないか、そんな心の声は嘘でない気がする。
こみ上げてくる不快さを抑えきれなくなって、恵太はたまらずスマホに逃避した。手にするまで目的は考えていなかったが、もはや習慣になりつつある行為を、体が勝手にとる。あの、どこにかけているのかも分からない番号を見つけ、通話をする。
何度繰り返しても、同じ展開が起きるだけ。幽霊どころか、誰かが出る期待もなく、恵太はただ留守電に切り替わるのを待っていた。意外性のない単調なコール音が、何度となく繰り返される。
恵太が息を呑んだのは、もうそろそろ留守電に切り替わるだろうかと考えていた時だ。コール音がぷつりと止まった。違和感を覚えながらも、留守電のアナウンスに切り替わるのを待ったがその気配はない。恵太はようやく事態を把握した。誰かが電話に出たのだ。急に心臓を掴まれた気になる。こちらからかけたのだから、何か言葉を発しなければ。そう、動揺する自分に言い聞かせた。
「えっと、もしもし」
息を飲む音さえ伝わりそうな沈黙が続く。間違い電話ということにして謝ろう、恵太が決意した時、
「何?」
と受話器から女の声が返ってきた。暗く、低い声。苛立ちや不信感といった負の感情は込められていない気がした。その代わり、歓迎している様子もない。電話を切ってしまいたい衝動を抑え、言葉をつなぐ。
「いえ、すみません。間違って電話をしてしまったみたいで」
「嘘」
「え?」
「私と話したくて電話してきたんでしょ?」
状況が掴めず、恵太の口からは「いや、あの」と気の抜けた声しか出てこなかった。誰なんだこれは。何が言いたいんだ。疑問ばかりのところに、淡々とした声が響いてくる。
「幽霊と話したいんでしょ?」
受話器の向こうで、女の口角がくっと上がった気がした。恐らく年齢は若いと思うが、それ以外は何も思い浮かばない。知り合いではないことは確からしかった。気味の悪さとともに、一つの仮説も浮かんでくる。どちらかというと、その説の方がよほど真実味はあった。
「すみません、これなんですか? イタズラですか?」
「あなたからかけてきたのに、イタズラ呼ばわりは酷いわね」
女の言うことはもっともだが。元が幽霊に繋がる電話番号という胡散臭いものだけに、電話をかけてきた相手を女がからかっているのが一番納得のいく可能性だった。
「あなたが期待した通り、私は幽霊なの。三年前に自殺したのよ」
タネが分かると、途端に滑稽に思えてくる。唯から苦労して手に入れたヒントとやらが、こんな安っぽい結末だったとは。虚しいと同時に、受話器の向こうの相手が憎たらしく思えた。
「すみません、死んでるところお邪魔しました。ではこれで」
耳からスマホを離し、終話ボタンに触れようとしたところだった。小さく聞こえてくる女の言葉の最後に、恵太の身は凍り付いた。
「あくまで信じないのね、ケイタくん」
落としそうになったスマホを、慌てて耳に押し付ける。
「今なんて言いました?」
「ケイタくんでしょ。それぐらい分かるわよ。こっちは死んでるんだもの」
聞き間違いではなかった。名前が知られている。スマホを押し付けている耳元から、汗が一筋流れ落ちる。誰なんだこいつは。目的は何なんだ。
「あんた、唯の知り合いか?」
攻撃的な口調になっているのも構わず、探りを入れた。
「ユイ? ユイちゃんは……あなたの大切な人。でも、死んじゃったのね」
ぐらぐら頭が揺れて、考えるのを止めてしまいそうになる。恵太は部屋の中を素早く見回し、当然なにも変わっていないことを確かめた。当たり前だ。何も起きてはいない。ただ、向こうが唯の知り合いである可能性が高くなっただけだ。
「なんだよこれ、悪趣味すぎるだろ。やめろよ」
「そう言われても。電話がかかってきたから話してるだけなんだけどね」
女はまるで動じる様子もなく、抑揚のない声で語りかけてくる。
「ケイタくん、きみ、何か目的があって電話してきたんじゃないの?」
恵太は何も答えなかった。唯が死んだ今、そもそもの目的だった『生け贄』の謎は知る必要もなくなってしまった。それよりも今は、この質の悪いイタズラのような状況を作った犯人を突き止めたい。この女は誰なのか、その疑問ばかりが頭を巡る。
「聞こえてる? 答えないなら、きみの考えていることを当ててあげようか」
勝手にしゃべる相手の言葉を、恵太は録音音声を聞くかのように聞き続けていた。
「きみ、死にたいんでしょ。だから幽霊である私に電話をしてきた。例えばそうね、死んだ後の世界のことを聞きたいとか、いい死に方とか、幽霊に聞けばいろいろ分かりそうだもんね」
だんだん相手が調子に乗ってきている気がして、恵太は苛立った。確かに死にたいと思ったことも、言ったこともある。全て見透かされている気がして、ますます気味が悪い。それでも、唯が死んだことまで挙げてからかってくる奴の言うことなど、到底認めるわけにいかない。自然と反論が口をついて出た。
「うるせえな、死んだヤツにグダグダ言われたくねえんだよ。死にたいなんて、思ってないしな」
「あら、やっと私が幽霊だって認めてくれた?」
「お前がしつこいからだろ。いいか、お前は死んだなんて嘘ついて、わざわざ手の込んだイタズラをしてる根暗野郎だ」
数秒の無音に、少しはダメージを与えられたかと期待した。ややあって「ふー」と聞こえてきた吐息は、どちらかというと『やれやれ』という億劫さを含んだ響きに思えた。
「一度、会って話さない?」
恵太は耳を疑った。
「マジで言ってんのかよ。自分の立場分かってないのか? 俺今、お前を殴りたいと思ってんだぞ」
心のどこかで、会って真相を確かめたい気持ちと、得体の知れない相手への不気味さがせめぎ合う。
「殴り飛ばすかどうかは、会ってから考えてよ。こうして電話してても、私が幽霊だって信じてくれないんでしょ?」
という言葉の裏は、会えば幽霊だと信じられるとでも言いたいのだろうか。躊躇いつつも、恵太は女と会う約束をした。この電話番号が、唯がヒントだと言って残したものということが頭に引っ掛かっていた。もう意味が無いと知っていても、無視をすることなどできなかった。
六
ショッピングモールのベンチで、間を空けて座る二人は傍から見ればどんな関係に見えるのだろう。いかにも学校帰りな制服姿の男子高校生と、一方は黒くて長い髪と白い肌が、作り物みたいに映える年上の女性。藍色のノースリーブから覗く腕も白く、雪国の生まれを連想させる。そのうえさらに整った目鼻立ちが人の目を惹きつけるのか、買い物客やカップルが振り向く視線を、恵太は隣にいるだけで何度となく感じることとなった。
恵太はもう何往復も、彼女の顔を目を耳を口を、体を、手を足を見ては、また顔へと視線を戻した。恐らく世の男がしたいその行為とは、違う視点で眺めていた。
「いや、どう見ても生身の人間でしょ」
率直な感想だった。自称幽霊女が『会えば分かる』とばかりに豪語するので、何が起こるのかと思えば、人間らしい人間が現れた。強いて言えば、その容姿の端整さは非現実的なのかもしれないが。
「じゃあキミが思う幽霊ってどんなの?」
電話と同じ、低く落ち着いた調子の声だ。電話で交わしたのは、翌日の夕方五時半にこの場所で会うという約束だ。まさか本当に来るとは。そして当たり前といえば当たり前だが、普通の人間が来るとは。半信半疑だった恵太は、二重三重に驚いていた。
「いや知らないですけど、心霊写真とかもっとボヤっとしてる、じゃないですか」
当面の迷いとして、敬語を使うべきかという点があった。電話で興奮してまくし立てた手前、必要ないかと思っていたが、目の前にすると気が引けてくる。恐らく三十にはなっていないだろうとはいえ、相手が年上なのは明らかだ。尚且つ、嘘をついて恵太をからかっている陰湿女、というイメージとは少し違っている気がしていた。
「ああいうのもあるかもしれないけど。ほとんどの人が気づいてないだけで、幽霊なんてこうしてそこら中にいるのよ。ほら、あの人も幽霊」
女が目立たないように指差した先には、自動販売機でコーヒーを買うサラリーマンらしき男がいた。
「いやいや。コーヒーとか飲まないでしょ、幽霊って」
言っている端から、男は缶を開け、その場で気持ちよさそうに一気に喉に流し込んだ。あれが幽霊だとしたら、この世の中の何を信じればいいのだろう。
「ふーん」
電話で聞いた覚えのある、吐息交じりの声。物憂げな仕草ひとつさえ、自称死人という非常識な前提がなければ見とれてしまいそうだ。女は膝の上の白いハンドバッグから、しなやかな指先で白いスマホを取り出した。肌だけでなく、持ち物まで白がよく似合っていると恵太は思った。
「ちょっと待ってて。今証拠を出すから」
何か見せたいものを探しているらしく、難しそうな顔をしながら指を滑らせている。自分のスマホがある辺り、どう贔屓目に見ても死んだ人間とは思えない。だがそもそもスマホを持っていないと電話に出られなかったわけで、そう思えば不自然ではないのか。などと一通り考えたところで、馬鹿らしくなって鼻で笑った。
「はいこれ読んで」
女が差し出したのは、インターネットのニュース記事らしかった。写真はないが、新聞のように大きな見出しに自然と目が行く。
『二十代の女性が飛び降り自殺』
潔いほどシンプルな見出し。横書きで詳細が書かれた記事の部分には顛末が連なっている。まだ記事を読んでいる最中なのに、女が何かを視線に割り込ませてきた。整っていながらどこか気の抜けて見える女の顔と、生年月日や住所、プラスチックの質感。運転免許証という印字を見るまでもなく免許証だ。女の意図を汲んで、名前を確認する。山岸遥、その情報と自殺の記事がどう繋がるのか。恵太は見たばかりの三文字の漢字を拾い逃さないよう、記事に目を走らせた。要点を飛び飛びに口ずさみながら、指でなぞる。さほど労することなく、記事の中段に標的の三文字を見つけた。
「亡くなったのは山岸遥さん二十五歳で、大学院生とありますね」
画面から顔を上げて女の様子を窺うと、力強い頷きがそこにあった。
「そう、それが私」
何か確信めいたように、薄紅色の口端が上がる。難解な数学の公式でも解けたような顔。恵太は女の満足気な顔に配慮して、控え目に問う。
「もしかして、これが死んだ証拠ってことっすか?」
「そうだけど?」
「でもこれって、たまたま同姓同名の人かもしれないですよね」
女は不満げに息をついたかと思うと、足を放り出したように座ったまま、吹き抜けになった通路の向こう側で遊ぶ子どもを見つめ始めた。指摘は的を射ているはずなのだが、こちらが間違っているような気にさせられて身動きがとれなくなる。
「そんな偶然まで気にしてたら、どうやって証明したらいいの」
自称幽霊女は言い終わりの合図のように、小さく唇を尖らせた。恵太は意識して目を逸らし、状況の整理に努める。惑いが生じそうになりながらも、恵太を奮い立たせる一つの感情があった。
「もうなんでもいいんすけど、結局何が目的なんですか? こんな信じるはずもない話のために、わざわざ会いに来たってことですか?」
一度切り込みを入れれば、あとは簡単だった。死んだ唯の話まで利用してからかおうとしている人間、そいつを黙らせたいというのが、恵太をここまで突き動かした動機だった。
「それはこっちのセリフでしょ」
幽霊女が、難しそうに寄せた眉のまま続けた。
「あなたが電話してきたんだから。何か用事があって電話してきたんでしょ? それともイタズラ? 私も死んでるとはいえ忙しいんだから、困るんだけどそういうの」
あくまでも死人として話してくる部分は聞き流すとして、恵太は言葉に詰まった。自分から電話をしたのは否定しようのない事実だ。この場合、どちらにイタズラとしての非があるのか、中立者に裁いて欲しい気さえしてくる。裁いてくれる人、から無意識に警官を思い浮かべて辺りを見渡したが、家族連れや学生が通り過ぎていくだけだった。短い現実逃避を終えて、恵太は腹を決めた。
「すみません、用事があるわけじゃなかったんです。それは謝ります」
「興味本位ってこと?」
「興味本位っていうか」
否定しようとしたが、他に納得のいく説明はできる気がしなかった。
「興味本位、かもしれないです」
女はまっすぐ視線を向けてくる。暗に責められているのか、他の意図があるのか、恵太には分からなかった。それでも掘りの深い大きな目は、安易な言葉を口にさせない威力があった。
「嘘」
電話の時にも、聞いた気がする声だ。何か恵太も知らない答えを知っているかのような、否定を許さない言い切り。面と向かった今、その言葉にはイタズラっぽい笑みが隠されていたことを知った。
「本当は、ユイちゃんのことが関係してるでしょ」
首筋から心臓まで、女の冷たい手でなぞられているような感覚。思わず目をやった女の手は、膝の上で上品に組み伏せられ、しっかり血色を帯びていた。生身の人間が相手だと再確認し、顔を上げる。
「俺の名前とか、唯のこととか、どうやって知ったんですか」
「それはね、なんて言ったらいいか」
言葉を探して女の視線がまた子どもたちがいた方へ向く。いつの間にか、吹き抜けの向こう側は通り過ぎる人影だけになっていた。
「超能力、って言っていいのかな。死んでからね、時々そういうのが分かるのよ」
漫画の中のような台詞を、真顔の大人から聞く日が来るとは思ってもみなかった。直面すると、現実の世界で口にすることの滑稽さが分かる。
「そういうのやめましょうよ。こっちはマジで気になってるんですよ」
「じゃあ、テレパシーかな? 私だってうまく言えないけど、キミと電話したとき、キミの名前とユイちゃんって子が死んじゃったってことは分かったの」
平行線を突き進む会話は、一向に回答に近づきそうにない。自分でも、どんな答えが聞ければ解決なのか分からなくなってくる。
「ねえ、よかったらその、ユイちゃんて子の話、私に聞かせてくれない?」
「唯の話を? なんで?」
敬語にし忘れた、と気づいたが言い直すのも馬鹿らしい気がした。
「なんでって、だってまだ若い子でしょ? なんで死なないといけなかったのか、気になるもの。それに」
女と目が合う。一瞬の間が、恵太に止まない瞬きを強いた。
「死んでる私なら、何かできるかもしれないでしょ」
恵太はぎゅっと目を閉じて、無理やり瞬きを押し込めた。痛くもないのに、こめかみに手を当て指を押し付ける。髪を触る振りで、何気ない仕草の中に隠した。
馬鹿げていると知りながらも、拭えない予感。期待感。その正体は、恵太自身にも分からなかった。ただ、唯が死んで以降の永遠に続くとも思える日常に、変化をもたらしたかったのかもしれない。その先にどんな結末が待っているのかは予想もせず、恵太は唯について話し始めた。
初めは遠慮がちに飲んでいたスポーツドリンクは、とうとうペットボトルの底四分の一ぐらいの高さにまで減ってきていた。残りが少ないことに気づいて、恵太は口に運ぶ量を舌先を湿らす程度に留めた。幽霊女が一方的に買って渡してきた時から、止めどなく話続けて今。唯が自殺したことを話すぐらいだと思っていたのに、女の質問に答えるうちに出会いまで遡ることになっていた。思い出していると歯痒さや虚しさに襲われそのたび言葉が詰まりそうになったので、飲み物でごまかせたのはありがたかった。
女は、時々質問はするものの、大よそ肯定するでも否定するでもなく、ただ神妙に恵太の話を聞いていた。ますます恵太には、女の目的が理解できないでいる。必然的に、唯が幽霊と話せる電話番号だと言っていた点にも触れることとなった。女がどんな反応を示すのか不安でもあったが、「そう」と拍子抜けするほど色のない返事があるだけだった。
「それで、キミはどうしたいの?」
恵太が無理やり笑い声を上げ、前向きな雰囲気にして締めくくろうとした後の、幽霊女の第一声。同調して笑う様子もない代わりに、静かに返事を促しているようだった。
「どうって? どうも無いですよ。話してくれって言われたから話しただけで」
結果的に一人で空元気に振る舞うことになって、乾いた笑い声が置き去りになった。
「そう? 少なくとも私には、まだキミがやるべきことはあるような気がするけど」
幽霊女の言葉とともに、左腕に固い無機物の感触が当たる。飲みかけの紅茶が入ったペットボトルの側面で、軽く小突かれた。恵太が何か反応する間もなく、幽霊女の言葉が続く。
「しょうがない、協力してあげるか」
「協力? なんの?」
言い終えると同時に、眼前にペットボトルの底面が突き出された。小突いた次はマイクにでも見立てたのかと思ったが、どうも指差しの代わりらしかった。
「なんの協力かは自分で考えなさい。ただ、当面の問題解決は手伝ってあげる」
訳が分からず、恵太はペットボトルの底に目を向けていた。ただただ、協力とやらの一方的な提案を聞く。
「その、莉花って子がなんか怪しいんでしょ」
「ああ、まあ」
「じゃあ、私が話を聞けるようにしてあげる」
「あの逃げ方じゃ無理っすよ。どうやって話聞くつもりですか」
「大丈夫。私、幽霊だし。なんとかなるよ」
次第に、揺るぎのない自信に満ちた態度に気圧されてきている気がする。
「話ができるようになったら連絡するから。そんなに何日もかからないと思うけど」
「そう、っすか」
「それより協力するにあたってお願いがあるんだけど」
恵太の投げやりな反応を察する風もなく、幽霊女は力強い目と口調で自分のセリフを強調してみせた。
「その、無理のある敬語やめてくれる? 電話の時の方がよっぽど威勢が良かったから。あんな感じでいいよ」
電話の時といえば、憤りもあって敬語を使う気など毛頭なかった。相手が見えないと感情にも任せやすかったが、女を目前にしては難しい気もする。
「そう、か?」
つまりは普段通り話せばいいはずなのだが、意識すると普段通りが分からなくなる。
「あと、私のことは本名で呼ばないで。死んでるのに本名で呼ばれると、さすがに目立つから」
「なんて呼べばいいんですか?」
幽霊女の眉が小さく持ち上がる。早速敬語を使ってしまったことへの牽制だろう。死人じゃないという否定は、いい加減不毛に思えてきたのでやめておいた。
「幽霊でいいんじゃない? あだ名みたいな感じで」
「幽霊って呼ぶってことですか?」
女の口が声を出さずに動く。『敬語』と窘められているのが分かる。考えるよりも先に、口をついて出てしまっていた。想定の内側の話なら気を付けられていただろうが、幽霊女の言うことは呼び名の案さえ想定の外側だ。
「だからそう言ってるでしょ。幽霊こんにちは、バイバイ幽霊」
「いやそれはおかしいって。本名より絶対そっちの方が目立つし」
「結構細かいこと気にするのね」
敬語でなくなったことに満足したのか、咎めるような仕草はみられない。代わりに半分呆れたように口を結んだ。
「じゃあ幽霊からとって幽ちゃんは? それなら変じゃないでしょ」
「幽、さんならなんとか」
「そう。じゃあ正式名称は幽霊で、愛称は幽さんね」
女が同意を求めて目を見てくる。幽霊と呼ぶのでなければなんでもいいと思い、恵太は頷いた。満足気に幽霊女も頷くと、軽く膝を叩いて「よし」と息をついた。
「じゃあ今日は遅くなっちゃったし、お開きにしようか」
どこまでも自分のペースで、幽霊女は事を運んでいく。
「待てって。莉花のことなんも知らないだろ。どうする気だよ」
「だから、死んでる人にそんな心配いらないんだって。超能力があるって言ったでしょ? もうその子のことはなんとなく分かったから、あとは連絡を待ってて」
それだけ言って、立ち上がった幽霊女は振り返ることなく歩いてエスカレーターの方へ消えていった。見れば見るほど生気を感じるその後ろ姿を、恵太は力なく見送った。
第三章
一
三十六個の机のうちの一個が花で飾られていたとして、学校の時間に大きな変化がある訳ではなかった。花だけ見てしまえば志半ばで消えた夢、無限にあったはずの可能性、生への希望、と訴え来るメッセージはあれど、現実は三十五個の日常と未来が大切だ。きっと、その机の主がもうここに現れないと知った日から、誰もがそうやって正当化している。教師も生徒も、最初の何日かは唯の死を悼む言葉を口にしていたが、十日も経てば花の水やりと交換だけが唯へ割かれる時間だ。それは本来三十六分の一として割かれる時間よりも、ずっと簡略化された扱いに感じられた。恵太よりもずいぶん速やかに、クラスと教師たちは本来の日常を取り戻すという作業を果たしつつあるのだろう。いなくなってしまえば、異を唱えるものもいない。死人に口なしとはよくできた言葉だ、と恵太は遠い世界のことのように感心した。
教壇に立って解説をしている数学の教師も、以前となに一つ変わった様子はなく授業を進めている。今となっては、唯の席を見なければクラスメイトを一人失ったばかりの教室とは誰も想像できないだろう。
恵太は、心許ない頭髪の数学教師が授業のたびにお悔やみを言う姿を思い浮かべて可笑しくなった。咳払いで口を覆ってごまかす。想像しただけで、あまりに不釣り合いだ。あの髪は、きっと公式に向き合うだけでは許されない、人間関係のストレスによって起きたものだ。生徒の死を悼み、残った生徒に気を配ることなど不向きだろう。勝手にそういうことにし、今の授業風景が正しいのだと結論づけて机に片肘をついた。
一昨日の幽霊女といい、考えれば笑いがこみ上げてくるようなことばかりだ。唯が死んだ衝撃で、自分の感覚は壊れてしまったのではないかと不安になる時もある。だが、思い起こせば幽霊女の方が非常識なのは揺るがない。あれに比べれば自分はきっとまだまだまともなのだと思い、自信を保つ。
机の下で、手持ち無沙汰にスマホを取り出す。新しい着信はないようだった。幽霊女は莉花と話しができるようになったら連絡すると言っていた。だが、その莉花の連絡先も顔も知らないはずだ。知っていたところでどうなるものでもないが、アクセスできないのであれば万に一つの可能性も起きようがない。
幽霊女の正体について、恵太は一つ仮説を立てていた。唯が、恵太をからかうために幽霊に繋がると嘘をついて、唯の知り合いの電話番号を渡してきた可能性だ。生け贄のヒントの真相がそんな話だとすると、随分と理不尽にも思えるがいろいろと説明はつく。唯と恵太の名前を知っていて当然という訳だ。問題は、唯と幽霊女の接点が思い当たらないことだ。唯に幽霊女のような知り合いがいるとは聞いた覚えがなかった。それに、唯が死んだ後まで続ける理由が分からない。
恵太はかぶりを振った。いずれどうでもいいことになっていく疑問だ。莉花と話せるようにするなどと不可能なことを引き受ける辺り、幽霊女はもう姿を現す気がないのだろうから。
あとは、自分の得体の知れない感覚が戻れば他のクラスメイトや教師と同じだ。恐らく恵太だけが今も持っている、喪失感? 後悔? 自責? 嫉妬? 名前をつけようと思えば付けられそうな、自分でも正体に気づいていないような、不安定な感覚。不思議なのは、そこに悲しいという感情を欲している気がすることだ。やがて時間とともに実感し、悲しみも湧いてくるものかと思っていたが、十日経っても変わらないとなると、その感情は一生起こらないのではないかと焦りさえ感じてくる。クラスの女子が泣いていたのが報せの翌日。話題にさえ上らなくなってきているのが、十日後の今。唯の死を悲しむ日が来ないというのは、正しいことなのだろうか。このままではいけない気がするという、体の内側にある違和感。その正体を知りたくとも、唯が死んでからあるのは、流され続けたいという疲弊した感覚だけだ。
物思いに割り込んできたのは、手元に持っていただけのスマホの画面だ。見慣れた数字の羅列が、真ん中に浮かび上がってくる。電話番号で届くショートメールだと分かり、恵太はスマホが震えるよりも早く指で触れ、メールの中身を開いた。
『莉花ちゃん話してくれるって。今日の放課後、三人で会うよう約束しておいた』
喉から漏れ出そうになった声を、必死で堰き止めた。周りを見やるが、不審に思われている様子はない。改めてメールを読み直す。内容が本当なら、たった二日で莉花と接触し、約束をとりつけたということになる。それができる可能性を、頭の中で探してみたが不可能としか思えなかった。一瞬、『幽霊』『超能力』という言葉が脳裏をよぎる。恵太はまた、自分がおかしくなってきたのか不安にかられることとなった。まずは本当か確かめてからだ。心の中で呟いたが、背中に滲む汗を止めるのは簡単ではなかった。
二
先に幽霊女とショッピングモールで合流し、約束しているというチェーン店の喫茶店に向かう。莉花の家がどのあたりかは知らないが、学校から自転車でも電車でも来やすい立地は、授業終わりでも寄りやすい。たとえ家が反対側の方向でも、それほど手間ではないだろう。恵太にとっては家と学校のちょうど中間あたりの場所にあるので、なおのこと丁度よかった。
ショッピングモール内一階の、飲食店が並ぶエリア。幽霊女は迷いなく進み、学生中心に姿が見える店へと入った。平日のためか席に余裕がある店内を見渡し、幽霊女は店員に窓側の席でもいいか尋ねた。速やかに案内され、店の外の買い物客が見える位置に座る。恵太もその後に続き、向かいに腰かけた。大きめのソファーが、恵太の体を軽く弾き返してくる。
「この店で間違えるってことはないと思うけど、よく窓の外を見ててね」
恵太は約束の時間と場所に出向いていてなお、幽霊女のタチの悪い冗談ではないかと疑った。必死で外を探す恵太に、舌を出して笑う女。そんな構図の方が、莉花がやってくるより遥かに可能性はあるように思える。幽霊女の指示に背くように、深く座ったソファーから目だけを窓の外に向ける。ほぼ同時に、恵太は腰を上げて目を凝らすこととなった。
「マジかよ」
「来たね」
恵太の視線が示す先に、幽霊女も莉花を見つけたようだった。白いシャツに青のネクタイ、襟元で着崩された、見慣れた制服。窓際から中を窺う様子もなく、足早に店内に入ってきて恵太たちの席を見つけた。
申し訳程度に恵太を一瞥し、幽霊女へ向き直る。繋がりの分からない二人の対面に、それぞれ紹介するべきかと恵太は迷ったが、莉花の様子がそれをさせなかった。何か言おうとしては口先で遮られ、ひきつけのような声を散らしている。その姿を前に、無感情な目で止まっている幽霊女。
「あの、わたしが」
莉花の声は辛うじて言葉として繋がり始めた。インタビューの時とも学校で逃げられた時とも違う、異様な追い詰められ方。右手で左の腕を抱き、寒気を抱きしめるように指先を食い込ませている。
「座って下さい」
もともと低めで落ち着いている幽霊女の声が、より暗い響きをもって発せられた。声色に突き動かされるように莉花は黙り、恵太の隣へ力なく座った。
「莉花さんですね、はじめまして」
幽霊女が口だけ動かして言うと、莉花は自分の膝元を見つめたまま会釈した。幽霊女の目が、莉花の動きから離れようとしない。恵太には、自分が芝居の世界に放り込まれたエキストラのように思えた。二人の関係性も、莉花を呼び出した方法も、想像するのは困難であり、口を挟む余地もない。ただ二人の作る空間に調子を合わせていると、勝手に背筋が伸びていることに気づいた。
幽霊女が莉花に飲み物を勧めるが、莉花は答えようとしなかった。店員を呼んだ幽霊女が、紅茶を三つ頼む。
「もうお分かりかと思いますが、私があなたを呼び出した者です」
莉花は決して視線を動かそうとしないが、小さく頷くことで相槌を示しているようだった。莉花の耳に届いていることを確かめているのか、空白を挟みながら幽霊女は続けた。
「私が、唯の姉です」
「なっ」
恵太は声を漏らし幽霊女を見たが、すぐに別の展開にかき消された。
「ごめんなさい」
絞り出された声に、視線を隣にやることになる。テーブルの下の膝に置いた手は見えないが、拳を握りしめているのではないかと思った。そうでないと不釣り合いなほど、莉花は身を固くしていた。
「私のせいなんです。私のせいで」
そこで莉花の言葉は止まった。続きの言葉を、恵太は容易に想像できた。恵太も、恐らく莉花も、口に出せば壊れてしまいそうな、割れ物の感触が歯止めをかけて声が出せない。
「唯は死んだ、と。そういうことなの?」
幽霊女がいとも簡単に代弁する。
「いや、さすがにそれは無いんじゃねえの。唯は、自殺したんだろ」
たまらず恵太は割って入った。否定しても、莉花の態度が並大抵ではない罪悪感を訴えてくる。その口から飛び出そうとしている告白は、受け入れられるものなのか。躊躇いが、恵太に真っ当な考えを主張させる。
「唯と莉花は一回しか会ったことが無いんだぞ。その一回だって大して話したわけじゃないし」
「一回だけじゃない。あの後、私たちはまた会ったよ」
テーブルに紅茶が運ばれ、陶器のかち合う音がする。空気に霜が降り、ひびが入る音のように思えた。莉花は唯の友人と親族からの視線を避けるように、目を伏せたまま続けた。
「あのヘイロの話をしてから、唯から連絡があったの。インタビューが中断になってごめんって」
唯から知らされていない、莉花との繋がり。恵太は唾を飲みこんだ。唯の死の真相を聞き入れろと、言い聞かせる合図のような喉の渇き。
「それからやりとりしてるうちに、もう一度、今度は二人で会おうって唯が言い出したの」
莉花が遠慮がちに、恵太を横目で見る。
「坂井は、また付き合わせるの悪いからって言ってた」
返したい言葉はなく、恵太は頷きで続きを促した。それを受け莉花がまた話し出す。
「それで、会ったの。そしたら」
核心に近づいてのことか、莉花は口元を震わせまた声を詰まらせた。
「お願い、本当のことが知りたいの。話して」
幽霊女があくまで唯の姉を装って、諭すように声をかけた。恵太は顔に出さないようにしていたが、遺族を騙るやり口に不信感もあった。事が済んだら問いただしてやると決め、ひとまず黙認する。
「私が、あんなこと言わなければ」
「何を言ったの?」
まるで本当の肉親のように、幽霊女が身を乗り出す。莉花の言葉を待つだけになった時間は、随分長く感じられた。誰も手をつけない紅茶が、ほのかな香りを放ち続けている。痛々しくさえある莉花を見ているのが耐えられず、恵太はテーブルの上を見つめた。
「私が」
唐突に再開された言葉に、恵太は耳だけ意識を向けた。
「飛び降りようかなって、言ったんです」
莉花はスイッチを押されたかのように動きを取り戻し、言い切った。抑揚の乱れた掠れ声。隣を見ずとも、涙混じりになっていることが分かった。
「あなたが? どうして」
怪訝な顔で幽霊女が尋ねる。
「後追い自殺か」
思わず呟いていた。莉花と出会うきっかけでもあった、ロックバンドにまつわる都市伝説とも言える噂。莉花と飛び降りというキーワードから、自然に導き出されるもの。莉花は否定も肯定もせず、唯と二度目に会った日のことを話し始めた。