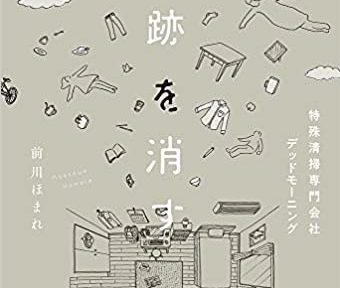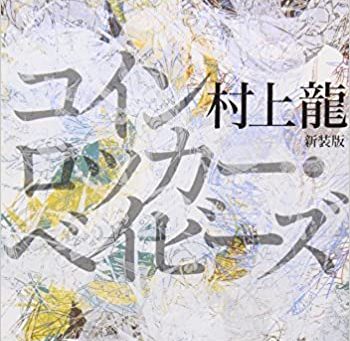作品が完成したら即応募…ではなかなかライバルたちを退けていい結果を出すのは難しいといえるでしょう。
では〆切のどれぐらい前に第一稿を完成させるべきなのか。
逆算していくと理想的な創作スケジュールが見えてきます。
ちなみに推敲の仕方や便利なツールについては以前の記事をご参照ください。
ついに第一稿が完成!次にやることは…?
まずは、小説を完成させるまでの流れをシミュレーションしてみましょう。とはいえ書くスピードも執筆に当てられる期間も作品の長さも人それぞれ。そこにどれぐらいの期間がかかるかについては、過去記事でも検証しているためそちらをご参照ください。
というわけで、ここは念願の念願の第一稿が完成したばかりの世界。
初心者さんもベテランさんも、このときばかりは高揚感や安堵感に浸るのではないでしょうか。あるいはその後に来る推敲というパートへ気合を入れなおすという方も多いかも?
そうなんです、第一稿が完成したからといって戦いはまだ続きます。というか、ここからが本番だという説まであるほど。
きました、推敲の時間です。
「よっしゃ、やってやるぜええええ」と原稿に向かおうとしたそこのあなた、ちょっとお待ちください!
 ?
?誰だ!俺を止めるのは!早く推敲をさせやがれえええええ!
すごい情熱…ですが、創作業界のセオリーにこんな言葉があります。
第一稿が完成したら、1か月は放置せよ
……まあ、管理人が今考えた言葉なんですけど。
ですが、ウソではないんです。管理人が読んできた創作論の書籍でもよく見かけたことですし。
なにか紹介できる根拠がないかと検索をしてみましたが、根拠らしい根拠は見つけられず。なぜ一か月なのか、本当に放置した方がいいのか…その疑問に答えてくれる方はいないかと探したところ。
管理人の手持ちの書籍にありました。それはたびたび当ブログで引き合いに出される、スティーヴン・キングの推敲スタイル。
書籍「スーパー編集長のシステム小説術」にはこのような記載があります。
キングは一旦原稿が完成したあとに、すぐに推敲に取り掛かることをしません。六週間は何もいじらず、覗くこともしないで、引き出しの奥に眠らせておきます。いかがでしょう、あのスティーヴン・キングが六週間眠らせるんです。たった一人の創作スタイルを挙げたに過ぎませんが、そこには原稿を眠らせるメリットがあると考えるべきでしょう。
そして別の仕事に取り掛かるのです。一か月と半分経ったところで、引き出しの中から取り出して、メモ用紙に問題点を書き出してゆきます。構成や人物造形に問題点を発見することが一番多いといいます。
では次に、そのメリットについて考えてみます。
原稿を眠らせるメリットとは?
メリットその1 書き上げハイを落ち着かせることができる
一番のメリットはこれではないでしょうか。第一稿を完成させた直後、誰もが体験する「書き上げハイ」を鎮める効果があります。
なにせ創作を試みた人のうち、長編を最後まで完成させられるのは1割程度と言われているほど大変な行程。完成できた時点で誇らしいと思ってもいいのかもしれません。そりゃテンションも上がるというもの。
長らく待望した先にようやく出会えるという意味では、出産と似ているかもしれませんね。そういえば、出産のときも産後ハイによるリスクを聞いたことはありませんか?
産後ハイによって危惧されるリスクそれは……キラキラネームの命名です!
わが子が生まれた瞬間は、「もう世界一かわいい!私だけの天使!」という気分になるのは自然なこと。ですが、その勢いで「エンジェルちゃん」や「プリンセスキャンディちゃん」などの目立ちすぎる名前をつけると…
100%失敗とは言いませんが、やはりしばらく経って後悔する可能性もありそうです。
そしてこの、産後ハイとよく似た現象ともいえるのが書き上げハイというわけです。

オレッちの名作と、キラキラネームを一緒にするんじゃねえ!
小説に関しては、自分以外の人が読んで面白いことに意義があるわけですから(少なくとも賞レースなどを目指すなら)、他人が見てどうかという視点が必ず必要です(二重表現になってしまうほど必要です)。
そのためには、一旦クールダウンが必要なわけです。子離れの時間をもつわけですね。
最低一か月、大切に書き上げた我が子と離れてみましょう。
自分が冷静になって再会した我が子には、きっとまだたくさんの伸びしろが見つかるはずですよ。
メリットその2 新規読者に近い目で作品と向き合うことができる
これはミステリーや壮大なファンタジー作品などで特に気をつけることかと思いますが、読者から見たとき、作品に登場してくる情報量は適切でしょうか?
たとえば作者の頭の中にはあるからと、作者しか知らない造語や人物名がどんどん出てきたらどうでしょうか?
ほどよい量であれば読み手も、「読み進めればわかってくるかな」と許容できますが、あまりにこうした描写が多いと読むのが嫌になってきます。
反対に、情報が出てこなさすぎてもダメですよね。作者の頭の中にはこういう人物で…といくら設定があっても、実際に描写がされていない人物がいきなり犯人でした!とかヒロインです!となっても読者は置いてけぼりです。
読み手が心地よい作品を作るには、作者の頭の中のストーリーや設定、伏線などを読者と共有することが基本なわけです。もちろん作品によって例外もありますが、ひとまず基本としては、です。
しかし、どうしても作者側は全貌を知っているだけに、何も知らずに読み始める読者側とは作品への印象に差が出がちです。
そこで作者側が少しでも客観的に自作を見る方法として、完成から一か月間を空けるという方法が有効になってきます。
もちろん、作品全体を忘れるということは不可能ですが、一か月も経つと初見に近い気分で読める部分も出てくるはずです。
一か月前の完成直後に読んだときと比べてどうでしょうか? ここの部分が説明臭くてわずらわしいなとか、急な展開で読者が置いてけぼりになっているななど、より鮮明に分かるようになっているはずです。
メリットその3 文章のぜい肉を発見しやすくなる。描写の自力がつく
以前の記事でもあげましたが、推敲≒削除と言われるほど推敲においてムダな文章を削っていくことは大事とされています。
でもですよ…そうは分かっていても、削除するってけっこうな勇気がいることだと思いませんか?
せっかく書いたのに…こんなにカッコいい文章、消すなんてもったいなさすぎる!
そんな風に思うのは自然なことだと思います。管理人自身も執筆後は思いますから…なんとかしてひねり出した文章を、なんとか生かせないかと考えるわけです。
しかしここは先人たちの助言どおり、まずはだまされたと思って一か月以上作品から離れてみることにしましょう。
するとどうでしょう、あんなに執着していた自分の文章に対していい意味でドライになれるんです。
「まあ確かによく書けたところだけど…無い方がテンポがいいな」とか「カッコつけてるだけで結構スベッた文章になってるわ…」とか。
少しでもそう思ったところはぜい肉と言える部分です。作者がそう思ったなら、読者はその10倍思うかも。ぜい肉はどんどん削っていきましょう。
自分の書いたものと改めて向き合うわけですから、ある意味ちょっと恥ずかしい経験かもしれませんが…そんなのは最初のうちだけ。
どうせこれからたくさん作品を書いていくのなら、すぐに気にならず、当たり前のものとして続けられるようになります。
そしてこの繰り返しで自作のクオリティを上げていくと、必然的に筆力もついてくるというわけです。良い描写、ムダな描写というものが染みついてきますからね。
結論:〆切の2か月前には第1稿が完成していることが理想
ここまで、推敲に取り掛かるまでに一か月間は第1稿を眠らせておいた方がいいということについて触れてきました。では、実際に推敲にかかる時間はどの程度なんでしょうか? 当然個人差や作品にもよると思いますが…管理人は一か月程度を推敲期間と考えておくと安心して執筆を進めることができます。
実際には400字詰め×400枚程度の長編で、3週間ぐらいの推敲期間だったイメージですが、〆切直前になればなるほど焦ってきますからね…
体調不良やPCトラブルなど不測の事態も踏まえ、少しゆとりがあった方がよいと思います。
また、推敲に必要な期間はプロットがどの程度練られていたかにもよってきます。根本的に直したり、追加したりするシーンが多ければ多いほど手入れに必要な時間が長くなるのはイメージしやすいかと思います。
書いているうちに新しいアイディアが湧くのは良いことであり楽しいことですが、物語の根本がひっくり返ることは無いよう、幹となるプロットは明確にしておきたいところですね!
こうして考えると、推敲一か月、その前の眠らせておく期間一か月で計二か月ほどかかる計算です。
〆切の二か月前には、第1稿が完成しているというイメージでスケジュールを組むのが一案でしょうか。もちろん、それよりも余裕があるに越したことはないですが。
いずれにしても、執筆は大変な労力・精神力を使うものです。〆切直前で身を削りながら書くようなことがないよう、スケジュールの組み方も新人賞を目指すためには大切なことと言えそうですね!
おわりに
新人賞をめざすため、ということで推敲への考え方やスケジュールの組み方を考えてみました。ただ、作品のクオリティアップや自身の筆力アップということで考えると、web小説などでも推敲にゆっくり時間をかけることは大切と思われます。
管理人も、完成直後は傑作と思ったものが、後から粗だらけだったと気づくことなんてしょっちゅうですから。
作品が書けたときはとにかくうれしいものですが、大切な作品だからこそ、ゆっくり練り上げてより質を高くしていきたいですね。
なにせ、しつこいようですがあのスティーヴン・キングですら6週間は眠らせて自分の作品と向き合うわけですから…!
主観だけで作品を書くことがいかに無謀なことか、よく分かるエピソードだと思いました。
本日の記事は以上です。最後まで読んでくれてありがとうございました!@フォトフレームをもらったのに入れる写真が無い管理人kei